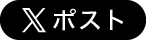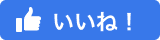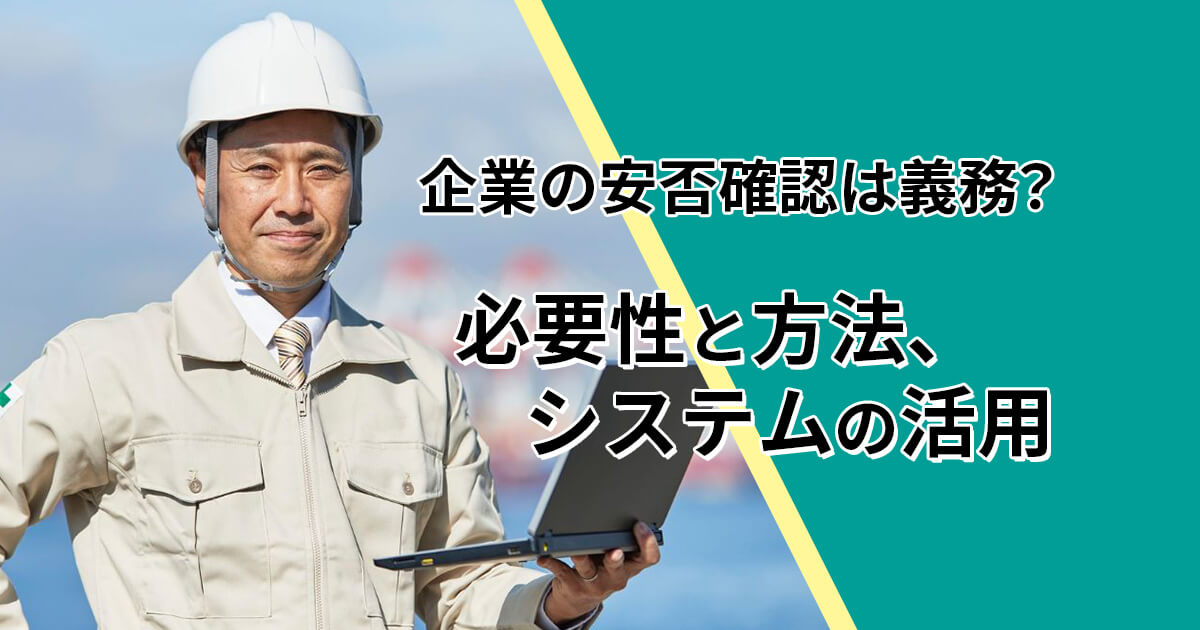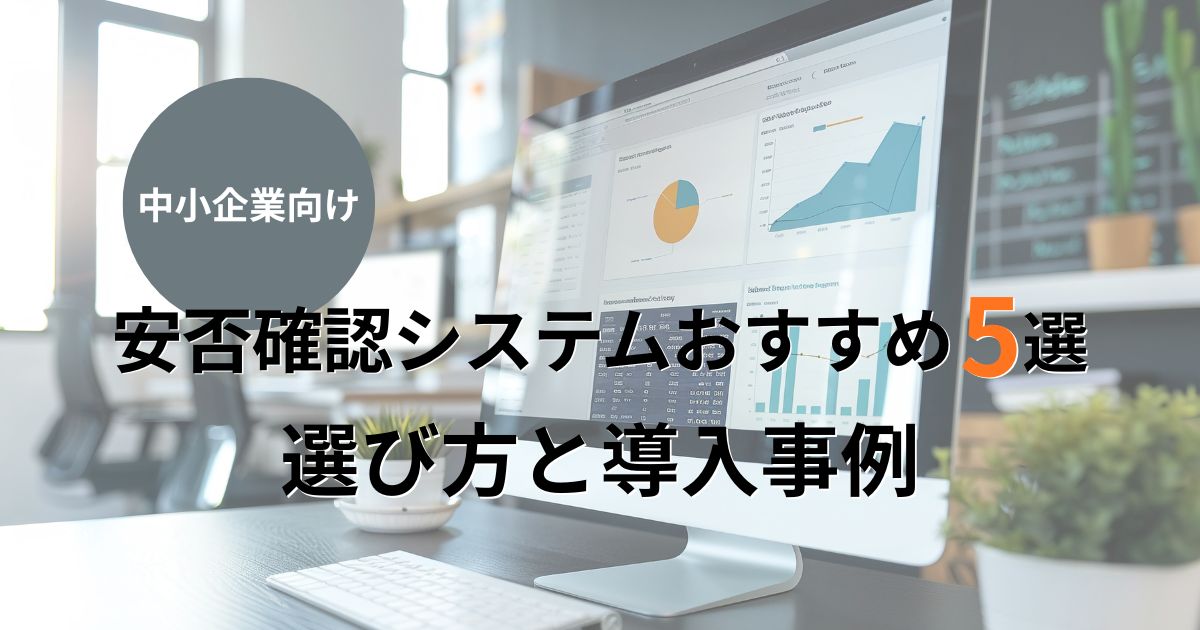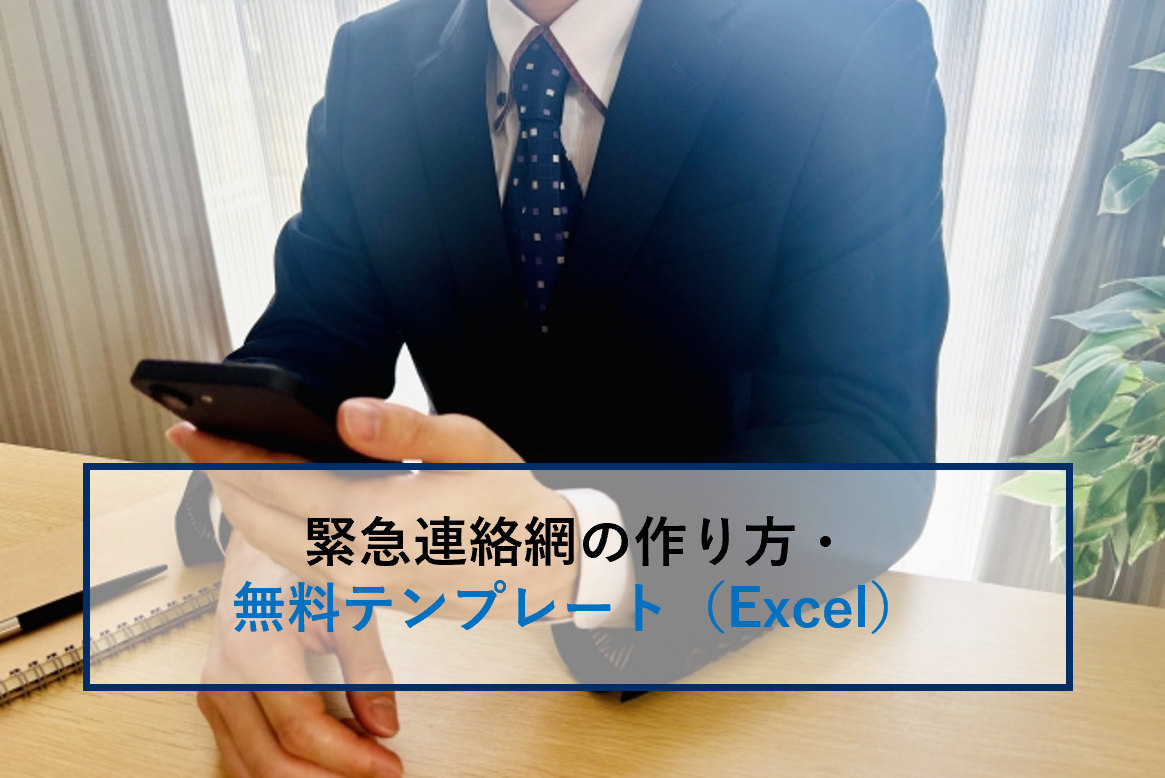目次
自然災害やパンデミックなどの緊急事態が発生した際には、従業員とその家族の状況を知るための安否確認が欠かせません。安否確認は企業の義務ではありませんが、安否確認を適切かつ迅速に行うことで、その後の初動対応や二次災害防止につなげられます。
この記事では企業における安否確認の必要性やその方法、手段などをまとめました。安否確認システムについても詳しく紹介しているので、導入を検討している方はぜひ最後までご覧ください。
企業における安否確認の必要性とは
安否確認とは、自然災害やパンデミックなどの緊急事態発生時に、従業員の安否状況を確認するために行う初動対応です。企業の方針によっては従業員だけでなく、その家族の安否確認も同時に実施する場合があります。
安否確認は企業の義務ではないものの、緊急状況下では人命がもっとも優先されるため、安否確認をスムーズに行える体制を事前に整備することが求められます。従業員の安否状況を収集し、適切に指示を出すことで、二次災害の防止にもつながります。
かつ、事業継続の面で考えても、従業員の安否確認は非常に重要です。緊急事態発生時は被害状況や稼働できる人員などの情報を集めたうえで、事業継続に必要な対応を判断します。その初動の動きとして、安否確認は非常に重要な役割を担っています。
企業の安否確認は直接的な法的義務はないものの、上記のように従業員の命を守る意味でも、事業継続の面でも責任が生じるため、体制を構築することが必要です。
企業における安否確認の方法
企業の安否確認は、事前に情報の整理と体制の整備が欠かせません。
まずは緊急時につながる連絡先を確保し、安否確認の手順をあらかじめ定めておきましょう。安否確認の担当者が全従業員に直接連絡する方法のほか、緊急連絡網のルールに従って安否状況を確認する方法もあります。緊急事態発生時に全従業員の安否をスムーズに確認するためにも、連絡先は複数確保しておくことがポイントです。
緊急事態発生時、安否確認の担当者は従業員に次の行動を指示したり、未回答者に追加の連絡を取ったりなどの対応を行うため、収集した安否情報を迅速にまとめる必要があります。全従業員の安否状況をできるだけ早く取りまとめるための体制や仕組みを構築することも重要です。
企業の安否確認の手段

システムの導入なしで使える電話・メールは企業規模によっては緊急事態に不向きな場合もあります。それぞれの特徴を踏まえた上で、自社に適切な手段を導入しましょう。
電話
電話を使った安否確認は、各従業員の電話番号に直接架電して行います。「誰が誰にどの順序で連絡するか」をまとめた緊急連絡網を事前に作成しておくことが重要です。緊急連絡網では電話がつながらない従業員がいた場合の対応や、安否確認の担当者への報告方法などのルールも一緒に定めておきましょう。
電話での安否確認は個別の情報を詳しく確認できる、多くの人が使い慣れた通信手段のため連絡しやすい、などのメリットがあります。しかし、大規模災害の発生時は、通信障害などによって電話がつながりにくくなる状況が発生しやすいため注意が必要です。
そのほか、相手が電話に出ない、安否状況を手作業で収集するのは時間がかかるなどのデメリットがあります。
メール
メールを使った安否確認は、一般的に安否確認の担当者がメーリングリストを使い、一斉送信して行います。通常の業務で利用している連絡手段を使うため、初期費用がかからない点はメリットのひとつです。また、全従業員に一斉に連絡できる分、電話で行う安否確認より時間がかからないという利点もあります。
しかし、電話と同様、通信障害が起きた際には大きな影響を受けます。メールが届かなかったり、遅延したりすると、スムーズに安否確認ができないため、担当者の負担も増大してしまうでしょう。従業員からの回答を確認し、集計する手間と時間もかかります。
安否確認システム
安否確認システムとは、従業員の安否状況を確認するための専用システムです。メールの一斉配信機能や自動配信機能、回答の自動集計機能などさまざまな機能で、迅速な安否確認をサポートします。
なかには、未回答者へ繰り返し連絡したり、従業員の家族への安否確認が可能だったりなど、より役立つ機能が搭載されている安否確認システムもあります。災害に強い安否確認システムなら、通信障害で電話やメールがつながらない場合でも確実性の高い安否確認が可能です。
安否確認システムはメールや電話などの手段に比べ、導入に費用がかかりますが、そのデメリットを上回るメリットが大変多くあります。次の章でご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
安否確認システムのメリット
安否確認システムの主なメリットを3つ挙げて、詳しく解説します。
安否確認がスムーズに行える
安否確認システムには一斉配信機能や自動配信機能などが搭載されているため、手間がかからず、迅速な安否確認が可能です。部署や拠点ごとなど自由にグループを設定できる安否確認システムが多く、必要な人へ適切に情報が届けられる点もメリットでしょう。
自動配信機能とは、「震度5以上の地震発生時に配信」など気象庁の緊急地震速報や津波警報と連動して、メールを自動で配信する機能です。担当者が被災してしまった場合にも、迅速に安否確認を行えます。ただし安否確認システムによって連動できる情報は異なりますので、自社の災害リスクに対応できるシステムを選びましょう。
従業員から返答がない際に繰り返し連絡する自動リマインド機能や、回答者の現在地が把握できるGPS機能などが搭載されている安否確認システムは、さらにスムーズな安否確認を可能にします。
管理の負担を減らせる
安否確認は配信して終わりではなく、全従業員の安否状況を把握したり、次の行動に活かしたりするために、回答の集計が必要です。
安否確認システムには回答の自動集計機能が搭載されているため、回答率や未回答者、被災状況、出社の可否などさまざまな項目を一気に集計できます。手動で行うより担当者の負担を大幅に減らせるのがメリットです。
安否確認システムによっては回答率などをグラフ化する機能があるため、混乱した状況下でも回答状況をスムーズに把握できます。
BCPを強化できる
上記でご紹介したさまざまな機能により、安否確認システムでは迅速な安否確認が行えるうえ、メールの送り間違えなどの人的ミスも防ぐことができます。安否確認は初動対応の要であり、安否情報を素早く整理することで、迅速な意思決定および次の対応へとつながっていきます。
人的被害の状況や稼働できる人員の把握は、事業継続においても非常に重要です。安否確認システムの導入・活用は、BCP(事業継続計画)を強化の第一歩になると考えられます。
緊急事態発生時に役立つ安否確認システムを導入するには、自社の災害リスクや現場に合ったシステムを選ぶことが重要です。以下の記事も参考にしてみてください。
安否確認システムの選び方
安否確認システムの選ぶ際は、複数のメーカーで相見積もりをとって費用を比較するほか、必要な機能が搭載されているかをチェックしましょう。特に重視するべき機能や、比較する際のポイントは以下の3点です。
- リマインド機能があるか
- 複数の手段で安否確認が行えるか
- 実績があるか
安否確認の確実性を高めるうえで、リマインド機能は重要です。未回答者に自動で連絡を繰り返す安否確認システムであれば、担当者の負担軽減にもつながります。その際、複数の連絡手段が可能かどうかも、重要なチェックポイントです。メールだけでなく、電話音声やアプリ、FAXなどさまざまな連絡手段が使える安否確認システムななら、従業員の回答率アップにつながります。
もっとも重視すべきは、安否確認システムの実績です。これまで大規模災害で問題なく稼働した実績があるか、導入社数が多いかなどを見比べて、信頼性の高い安否確認システムを選びましょう。
実績のある安否確認システムを選ぼう
緊急事態発生時に通信障害などの影響を最小限に抑え、確実に従業員の安否を確認するには安否確認システムの導入が有効です。特にこれまで大規模な災害で稼働した実績のある安否確認システムを選ぶと、緊急事態発生時に企業を強化にサポートしてくれるでしょう。
安否確認システムをお探しのご担当者は、東日本大震災や熊本地震での稼働実績がある「エマージェンシーコール」をぜひご検討ください。ひと通りの機能が揃い、オプションでLINE連携も可能なスタンダードプランのほか、従業員数300名までを対象としたリーズナブルなライトプランもあります。まずはお問い合わせください。