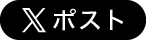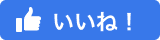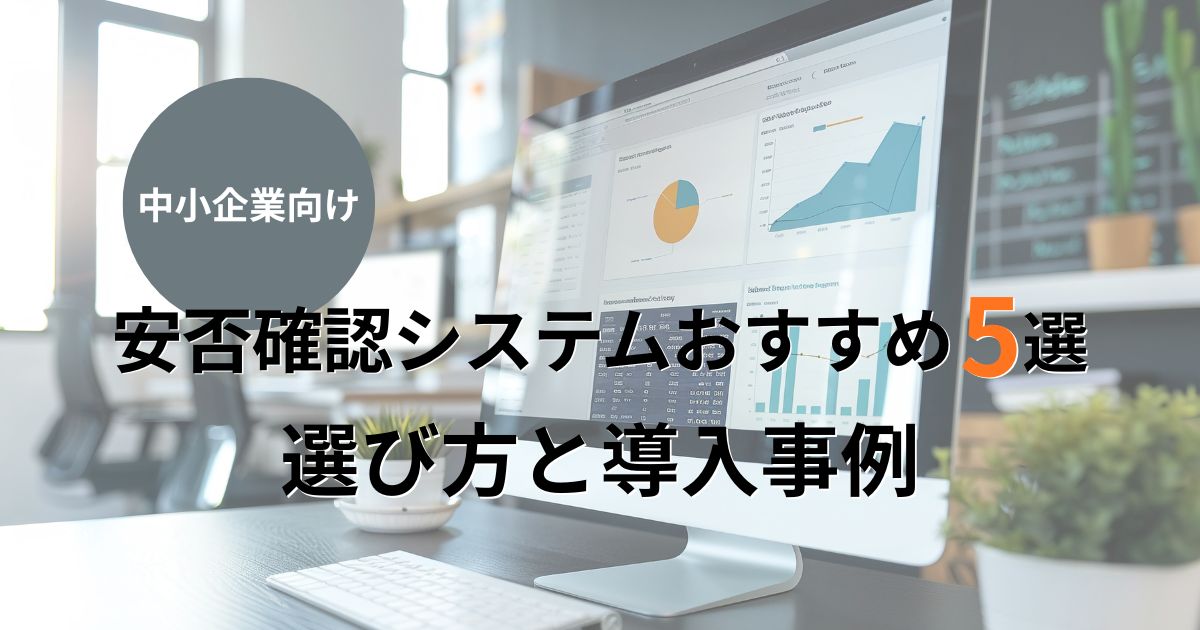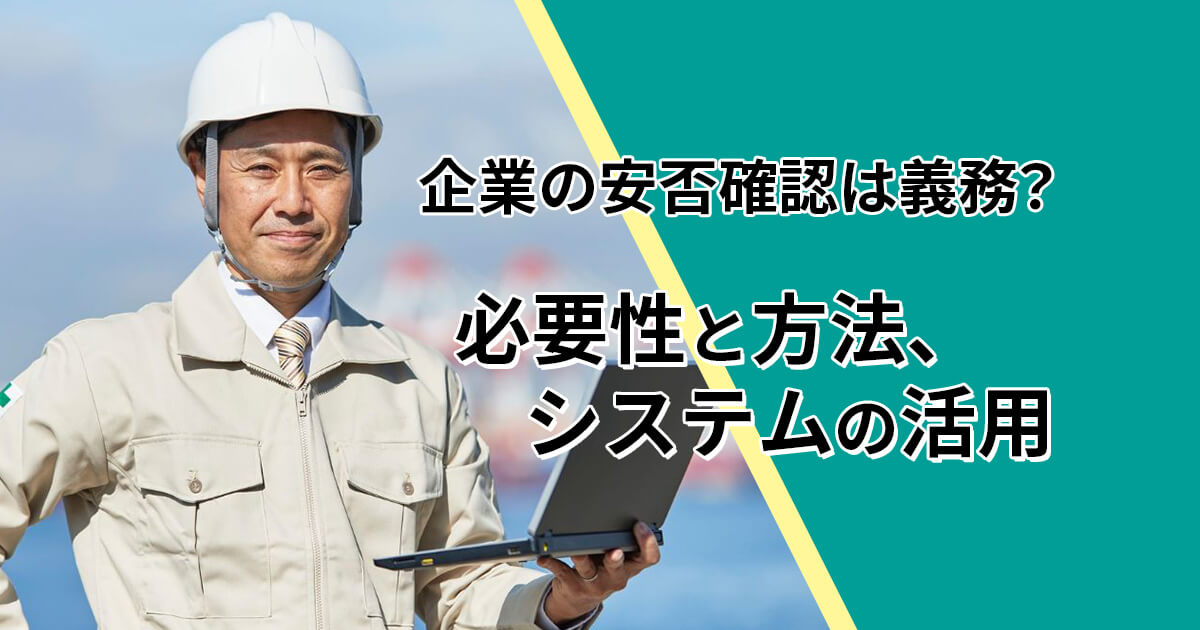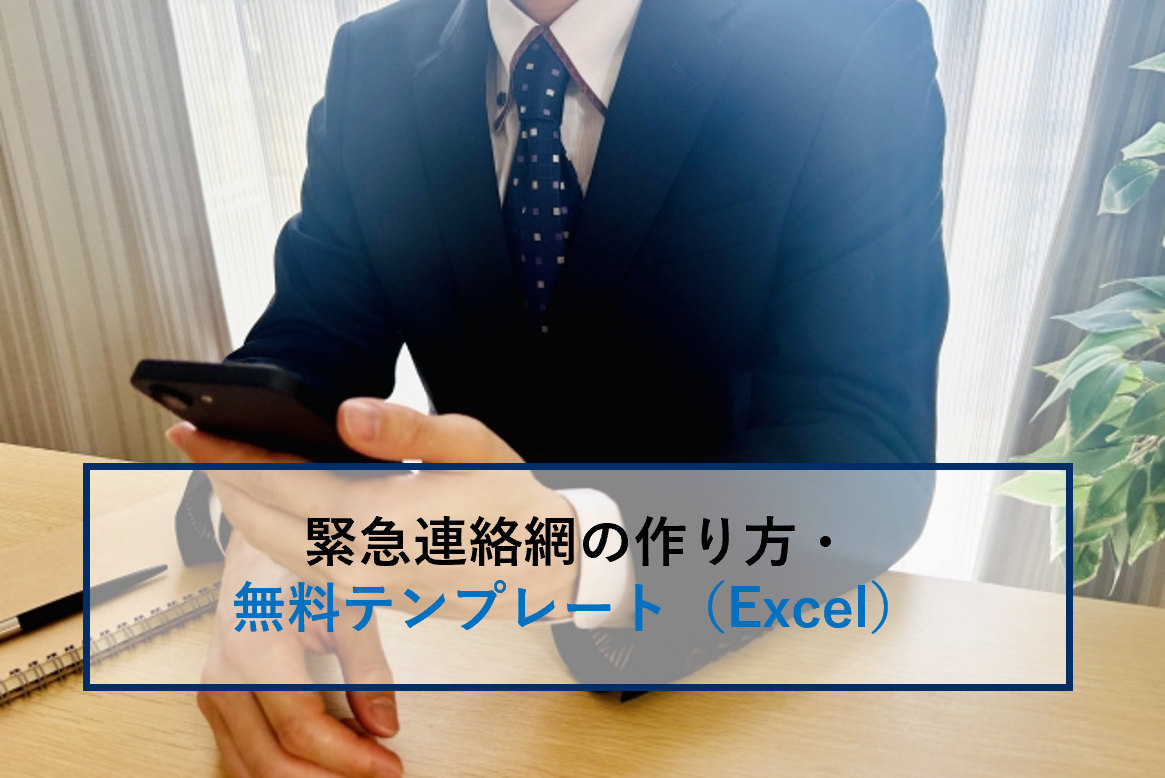災害時の連絡手段にはLINEなどのアプリやSNSのようにさまざまな方法があります。大震災や洪水、津波などが発生した際に家族や知り合いとスムーズに連絡を取るためにも、携帯が繋がらない場合を考慮して複数の連絡手段の確保が重要です。
この記事では災害時の安否確認に役立つ連絡手段を複数ご紹介します。停電が起きた際にも役立つ災害用伝言ダイヤル(171)や公衆電話、公衆無線LANサービスなどの情報もまとめました。
災害時における緊急連絡の重要性
災害時は被災地に通信が集中し、電話がつながりにくくなる可能性が高まります。緊急時に家族や知り合いと速やかに連絡をとり、安否確認を行うには、連絡手段の事前共有が重要です。
また、通信規制や停電が起きた場合に備えて、さまざまな通信手段をあらかじめ確保しておくことも大切です。
災害時に役立つ連絡手段や方法7選
大震災や津波、洪水など災害が起きた際に役立つ連絡手段や方法を7つご紹介します。
1)災害用伝言ダイヤル(171)
※携帯やインターネット回線が使えない場合にも利用可能
災害用伝言ダイヤル(171)とは、音声で安否情報を登録・確認できる伝言サービスです。固定電話をはじめ、携帯電話とPHS、公衆電話、災害時に避難所に設置される特設公衆電話で利用できます。1回あたり30秒の伝言が登録でき、登録できる最大の伝言数はひとつの電話番号あたり20件までです。
音声を録音する方法、確認する方法をそれぞれ以下にまとめました。
【音声を録音する方法】
- 「171」をダイヤルします
- 「1」をプッシュし、伝言を残したい電話番号を押します
- 30秒以内にメッセージを録音します
※「8」を押すと録音し直せます
【音声を確認する方法】
- 「171」をダイヤルします
- 「2」をプッシュし、伝言を確認したい電話番号を押します
- 伝言が流れるので、もう一度聞きたい場合は「8」をプッシュしてください
- こちらからの伝言を登録したい場合は「3」を押して音声を登録します
災害用伝言ダイヤル(171)は災害が発生し、通信がつながりにくくなった段階でサービスの提供が開始されます。災害時以外でも適宜、無料体験が実施されているため、あらかじめ使用方法などを確認したい場合は、ぜひ以下の期間に利用してみてください。
【無料体験の提供日時】
- 毎月1日、15日の00:00~24:00
- 正月(1月1日00:00~1月3日24:00まで)
- 防災週間(8月30日9:00~9月5日17:00まで)
- 防災とボランティア週間(1月15日9:00~1月21日17:00まで)
2)災害用伝言板
災害用伝言版はインターネットを利用して、安否状況を文字情報で登録・確認できる特設伝言版です。電話がつながりにくい場合でも、回線の集中を避けて安否情報の登録と確認ができます。インターネットが利用できる携帯電話やタブレット、パソコンなどで利用でき、1伝言あたり100文字のメッセージが登録可能です。
災害用伝言版は、以下のようにさまざまな企業でサービスが提供されています。
- 災害用伝言板 (NTTドコモ)
- 災害用伝言板サービス(au)
- 災害用伝言板 (ソフトバンク)
- 災害用伝言板サービス(Y!mobile)
- 災害用伝言板(web171)
このうち災害用伝言板(web171)の使い方を解説します。まずは利用者登録方法から説明します。災害用伝言板(web171)は事前登録をしなくても使用できますが、利用者登録をすることで、通知設定が可能になります。
【登録方法】
- web171へアクセスします
- 「新規の伝言板の登録」をクリックします
- 電話番号やメールアドレス、パスワードを記入します
- 伝言を知らせたい相手の基本情報を入れます
- 内容に誤りがなければ「登録」ボタンをクリックします
続いて、伝言の登録・確認方法の手順を紹介します。
【安否情報を登録する方法】
- web171へアクセスします
- 伝言を残したい電話番号を登録します
- 安否状況にチェックを入れ、名前・伝言を入力して登録します
【安否情報を確認する方法】
- web171へアクセスします
- 伝言を確認したい電話番号を入力します
- 伝言が表示されます
※伝言を確認したあとは自分の伝言の入力が可能です
災害用伝言板(web171)も災害用伝言ダイヤル(171)同様、無料体験期間が用意されていますので、ぜひ事前に使い方を確認しておきましょう。
【無料体験の提供日時】
- 毎月1日、15日の00:00~24:00
- 正月(1月1日00:00~1月3日24:00まで)
- 防災週間(8月30日9:00~9月5日17:00まで)
- 防災とボランティア週間(1月15日9:00~1月21日17:00まで)
3)公衆無線LANサービス 災害用統一SSID「00000JAPAN」
※携帯やインターネット回線が使えない場合にも利用可能
連絡手段とは異なりますが、通信障害が発生した際に活用できる通信手段として公衆無線LANサービス「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」を紹介します。
災害用統一SSID「00000JAPAN」は各通信事業者が提供している公共無線LANサービスを、災害や大規模な通信障害の発生時に「00000JAPAN」という共通のネットワーク名で無料開放するWi-Fiサービスです。インターネットを利用できる携帯やパソコンを「00000JAPAN」のWi-Fiにつなげば、携帯キャリアやパソコンの種類に限らずどなたでも利用できます。
4)LINE安否確認
LINE安否確認は、コミュニケーションアプリ「LINE」で利用できる安否確認手段です。震度6以上の地震など大規模な災害が発生した際に、LINEのホームタブに「LINE安否確認」のアイコンが表示されます。詳しい使い方は以下のとおりです。
【安否情報を知らせる方法】
- ホームタブに出現した赤枠内の「安否を報告」をタップします
- 「無事」「被害あり」のいずれかを選択し、必要に応じてコメントを入力したら「公開」をクリックします
【安否情報を確認する方法】
- 友達リストから「安否確認」をクリックします
- 友達の安否状況とコメントが一覧で表示されます
9月1日の「防災の日」や3月11日などに限定してLINE安否確認の体験版が提供されるため、使い方を予習しておきましょう。
5)SNS
以下のSNSが安否確認に利用できます。
上記SNSに自分の安否状況を投稿すれば、SNS上でつながりのある人々に安否を知らせることができます。またはDM機能やメッセンジャー機能などを使えば、特定の人物との安否確認が可能です。
6)公衆電話
※携帯やインターネット回線が使えない場合でも利用可能
公衆電話は災害時に通信規制の対象とならないため、携帯電話や自宅の固定電話が使えないときに役立ちます。また、NTTの通信ビルより電話線を通じて給電されているため、停電の影響も受けません。
ただし近年の傾向で、公衆電話は次第に数が減りつつあります。一方で災害時用公衆電話(特設公衆電話)は設置数が増えているため、事前に場所を確認しておくと安心です。公衆電話では、前述した災害用伝言ダイヤル(171)が利用できます。
7)災害用アプリ
災害用の専用アプリならグループチャットで状況を確認できたり、位置情報を共有できたりなど、さまざまな方法で安否確認が行えます。避難所の確認や災害情報の受け取りも可能なため、事前に入れておくと災害時に大いに役立ちます。アプリはキャリアのメールサーバーを使用しないため、通信が制限されている状況下でも利用が可能です。
ただし専用アプリを使い、家族や知人間で安否確認を行うには、全員が同じアプリをダウンロードする必要があります。
企業における安否確認はシステムの活用を!
企業での安否確認には、メールや電話よりも安否確認システムの活用がおすすめです。安否確認システムなら、自動で安否確認のメールを一斉配信したり、従業員からの回答を分析できたりなど、防災担当者の負担を減らしながらスムーズに安否確認が行えます。安否確認システムによっては、従業員の家族の安否確認も可能です。
安否確認システムを導入する際は、複数の連絡手段が備わっているシステムを導入しましょう。メールや電話以外に専用アプリやLINEなど複数の連絡手段が利用できるシステムを導入することで、通信規制が起きた際にもスムーズに連絡が取れるようになります。緊急事に安定的に稼働するシステムを選ぶためにも、過去の災害での稼働実績も確認しましょう。
安否確認システムのエマージェンシーコール
「エマージェンシーコール」は自動配信機能や回答の分析機能、未回答者のリマインド機能など、ひと通りの基本機能が揃った安否確認システムです。東日本大震災や熊本地震でも安定的に稼働した実績のある災害に強いシステムで、2025年6月現在5,200社に利用されています。
メール、電話音声、専用アプリ、FAXなど豊富な連絡手段を備えている点も強みです。さらに家族向け伝言サービスを提供しており、従業員のみならず、従業員の家族の安否確認をサポートします。
安否確認システムの導入をご検討中の方はぜひ注目してみてください。