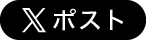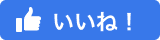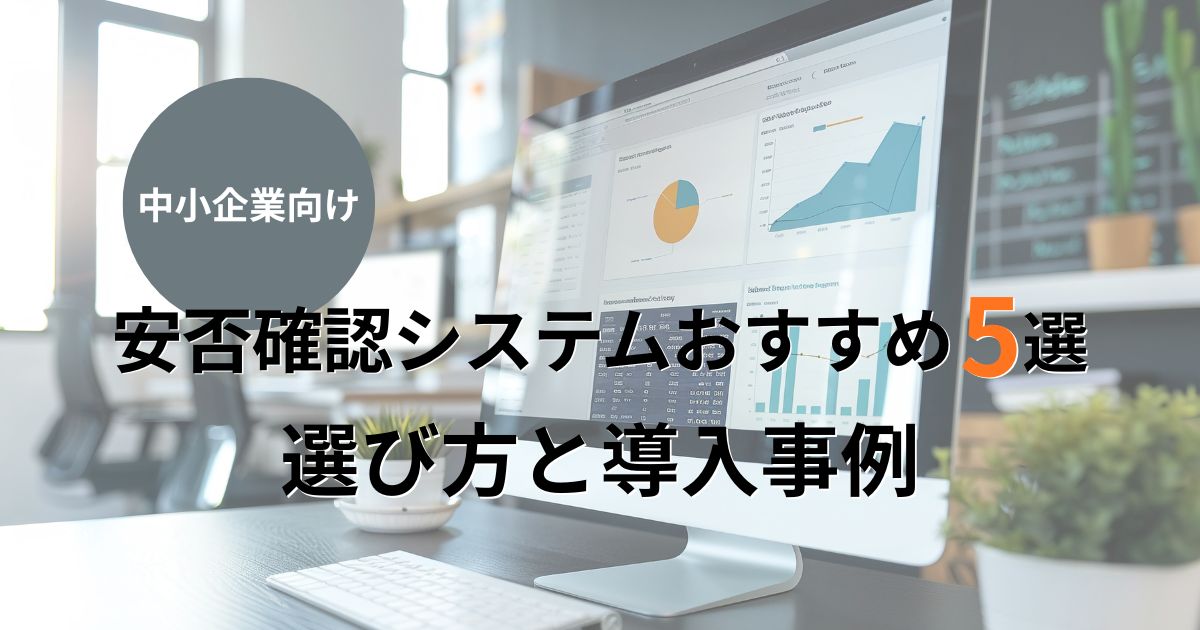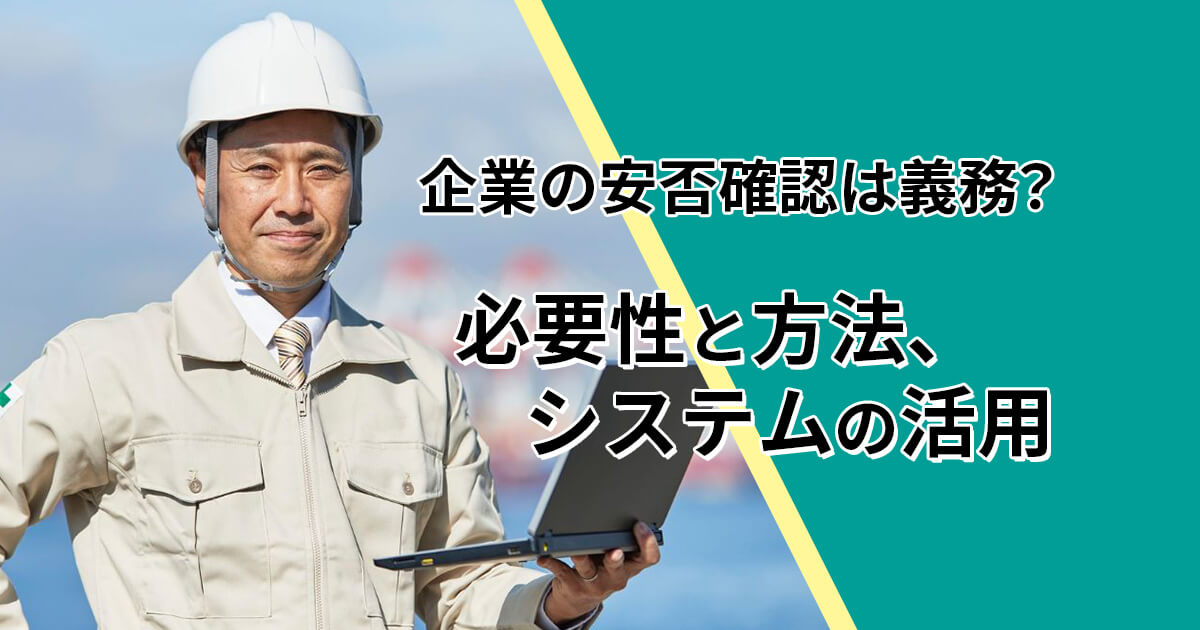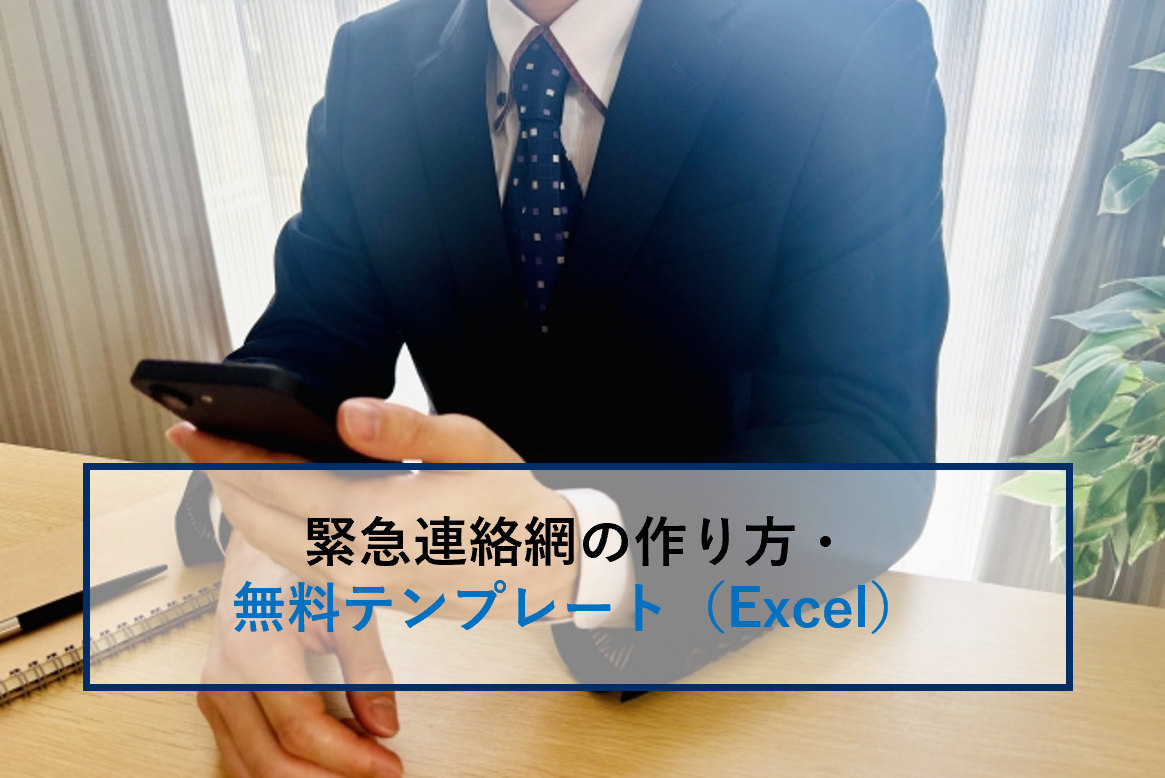目次
緊急時の初動対応のひとつでもある安否確認。いざというときに焦らず、迅速かつ適切に安否状況を確認するためにも、定期的な訓練の実施が欠かせません。
この記事では安否確認訓練について、実施の目的や手順などを詳しく解説します。安否確認訓練を実施する際の注意点やシナリオ作成のポイント、メール例文まで役立つ情報を網羅的にまとめました。
安否確認訓練とは
安否確認訓練とは、緊急時の初動対応のひとつである安否確認の実効性を確認するために行う訓練です。定期的に訓練を実施することで、安否確認の手順やルールを参加者に意識づける役割もあります。
企業には従業員の安全を守る安全配慮義務が課されており、災害時などにもその義務を果たすことが求められます。従業員の人命と身体の安全を守るためにも安否確認体制を整えることがまず重要であり、緊急時に従業員が正しく行動できるよう訓練を通して安否確認の手順を浸透させることが必要です。
また、災害などが起きた際に事業が長期間停止してしまうと、取引先や顧客にも大きな影響を与えてしまいます。企業としての社会的責任を果たすには緊急時に事業を停止させない計画が必要です。特に安否確認は、収集した安否状況をもとに次の対応を判断したり、事業の復旧に必要な人員を集めたりなど、事業継続の視点で重要な意味をもちます。そのため安否確認の体制を整えるだけでなく、必ず定期的に訓練を行い、緊急時の対応力を高めましょう。
安否確認訓練の目的

安否確認訓練を実施する主な目的を2つの視点で解説します。
1)実効性を確かめるため
前述したとおり安否確認訓練は、事前に体制を整えた安否確認の実効性を確かめるために行います。定期的に訓練を行い、問題点の見直しと改善を繰り返していくことで、より確実性の高い安否確認体制へとブラッシュアップしていけます。
たとえば安否確認メールを送った際の回答率が低い場合は、従業員が返信しやすいほかの連絡手段も考える必要があるでしょう。また、事前に訓練を行うことで、従業員の連絡先の記載間違いや変更作業漏れ、新入社員情報の登録不備などにも気づくことができます。
2)従業員の意識を高めるため
緊急時は焦って冷静に行動できないケースも考えられるでしょう。このような事態を避けるためにも、さまざまな災害や事故などを想定して、事前に安否確認訓練を行うことが大事です。繰り返し訓練を実施することで、従業員の防災への意識向上にもつながっていきます。
安否確認の手順
次に安否確認の手順を紹介します。自身の安否状況を伝える際は、二次災害に巻き込まれないよう自身の安全を確保したり、周りの状況を確認したりしてから行います。以下に手順とポイントをまとめました。
| 手順 | ポイント | |
|---|---|---|
| 1 | 自分自身の安全を確保 | 地震発生時は机の下に隠れるなど、まずは自分の身を守る行動を行いましょう。 |
| 2 | 周りの安全を確認 | 自分も含め、ケガ人がいないか確認します。ケガ人がいる場合は応急手当てなどを行います。 |
| 3 | 建物や設備など周囲の状況を確認 | ガラスの破片が落ちている場所や、崩れている部分がないかチェックしましょう。避難経路が断たれていないかも確認します。 |
| 4 | 担当者へ報告 | 上記で安全を確認したあと、もしくは安全な場所に移動したあとで確、現在の状況を責任者に報告します。人数などを正確に報告することが必要なため、あらかじめ報告用のフォーマットを定めておくよいでしょう。 |
安否確認訓練の流れ・方法
続いて、安否確認訓練を実施する流れを解説します。訓練は計画的に行い、見直し・改善を含めたプロセスを組み立てないと、十分な効果を発揮しません。以下で紹介する流れと方法を参考にしてみてください。
①シナリオを作成し、事前に訓練内容を周知
自然災害や火災などの非常事態はいつどんなときに発生するかわからないため、あらゆる状況を想定したシナリオを作成することが重要です。シナリオは以下の項目を盛り込んで作成しましょう。
- 発生したインシデントと規模(例:津波を伴う大規模地震など)
- 発生時間
- 訓練の対象者
- 訓練の手順
シナリオ作成のポイントについては後述するので、ぜひそちらの章もご覧ください。
シナリオが完成したら、従業員へ訓練内容を事前共有しておきます。事前共有を行わない抜き打ちの安否確認訓練も定期的に織り交ぜると、緊急時の対応力をより高めることができます。
②訓練実施
シナリオに沿って訓練を実施します。訓練中は安否確認の回答率や、返答までにかかる時間を測定し、BCPの見直し・改善における検証の材料にしてください。
回答者の年齢や、その連絡手段に慣れているかなどの違いによって、回答にかかる時間が異なる場合もあります。細かい部分まで記録を残し、後の振り返りに活かしましょう。
③安否確認体制の見直しと改善
訓練実施後は必ず安否確認体制の見直しと改善を行い、BCPの内容を更新しましょう。安否確認訓練の参加者にアンケートをとって、課題や問題点を洗い出す方法もあります。
たとえば「安否確認メールにどう返信すればよいかわからなかった」という意見があれば、「①被災あり/②無事(被災なし)」など選択回答形式するなど、従業員が答えやすいメール文に変える必要があるでしょう。
訓練の実施、見直し・改善というPDCAサイクルを回しながら、安否確認体制のブラッシュアップを行ってください。
安否確認訓練のメール例文
自然災害を例に安否確認メールをご紹介します。
【地震発生時の安否確認メール例文】
国内で震度6強以上の巨大地震が発生しました。
広範囲で被害がおよぶことが予想されるため、全従業員に発信しています。
地震発生地域にいる、いないに関わらずご自身の状況を回答してくださいますよう、お願いいたします。
■本人の安否状況 1.被災あり/2.軽度の被災あり/3.無事(被災なし)
■出社可否 1.可能/2.不可/3.不明
【気象特別警報解除後の安否確認メール例文】
○○(地域名)で発令された特別警報は解除されました。
安否状況の登録をお願いします。
該当地区に滞在している場合は引き続き気象情報を確認の上、安全に配慮した行動をお願いします。
■本人の安否状況 1.被災あり/2.軽度の被災あり/3.無事(被災なし)
■出社可否 1.可能/2.不可/3.不明
安否確認訓練のポイント・注意点

最後に、安否確認訓練を実施する際の注意点やポイントを解説します。
具体的なシナリオを作成すること
まずは「安否確認の手順を理解させる」「前回の訓練より安否確認の回答率を上げる」など訓練の目的を定めたうえで、シナリオ作成を行います。シナリオは発生したインシデントや時刻などを具体的に想定して作成することが必要です。
「東日本大震災を想定して平日の日中」など、過去の災害をもとにシナリオを作成するとより実践的な訓練となります。
| 目的 | 安否確認の回答率100%を目指す |
|---|---|
| 発生日時、場所、規模 | 2025年〇月〇日(〇)14時30分 東京湾を震源とする地震が発生 事業所のある地域では震度5強の揺れが観測された |
| 被害状況 | 負傷者は0人 事業所内で備品や書類は散乱しているが、電話やインターネットには影響なし ただしが余震が続いているので注意が必要 |
| 訓練内容・手順 | 以下の流れで実施 ①安否確認システムを用い、安否確認のテストメールの一斉送信 ②安否状況を回答 ③担当者が回答状況の分析を行い、報告 |
安否確認システムがスムーズに使用できるかチェックすること
安否確認訓練では、従業員が適切に安否状況を報告できるかだけでなく、担当者が安否確認システムを問題なく使えるかもチェックすべきポイントです。
安否確認システムがうまく作動するか、従業員の安否状況が問題なく収集できるかなどをチェックし、非常事態に備えましょう。
従業員への理解を得ておく
「日々の業務で忙しいなか、安否確認の返信をするのは面倒…」と考える従業員がいた場合、担当者も対応に困ってしまうでしょう。意味のある安否確認訓練を実施するには、事前に従業員から理解を得ておくことが重要です。
あらかじめ安否確認の意味や怠るとどのような事態が起こり得るかなどを伝えると、安否確認の重要性を理解してもらいやすくなります。
休日など業務時間外の訓練は強制できない
自然災害などの緊急事態はいつ発生するかわからないため、休日など業務時間外の訓練も想定する必要があります。
業務時間外の安否確認訓練は違法ではありません。また、回答作業に多大な時間がかかるわけではないため、残業扱いも基本的には不要と考えられます。しかし、業務時間外の訓練参加は強制できない点には注意しましょう。
実践的な安否確認訓練で緊急事態に備えよう
安否確認の実効性を高めるためには、定期的な訓練が欠かせません。実施して満足するのではなく、必ず見直しと改善を行うことで、よりBCPの有効性を高めていくことができます。訓練を行う際は実施から見直し、改善までのプロセスを考え、計画することが重要です。
安否確認をより効率的に行いたい場合は、安否確認システムの導入を考えましょう。東日本大震災でも稼働した実績のある、災害に強い「エマージェンシーコール」をぜひ検討してみてください。