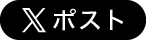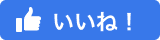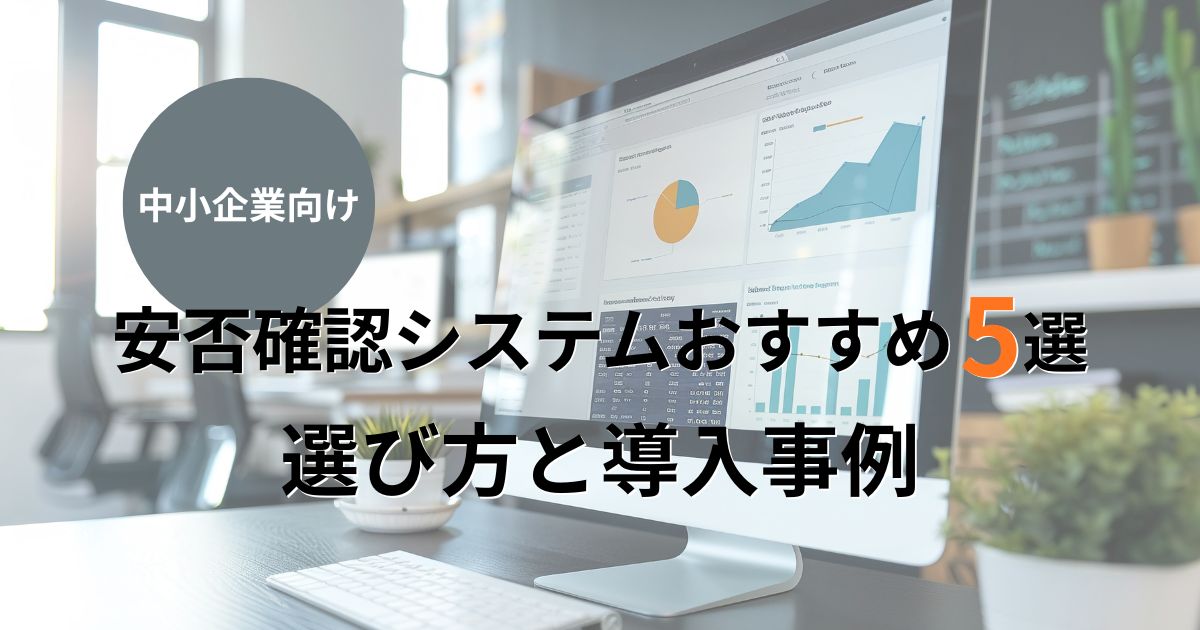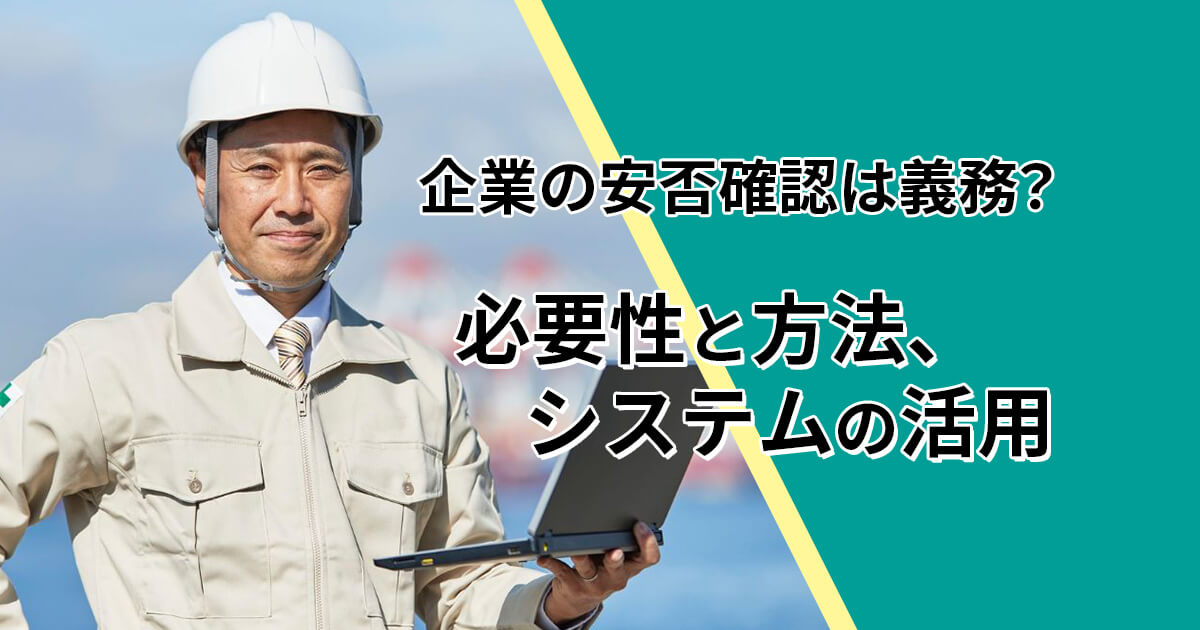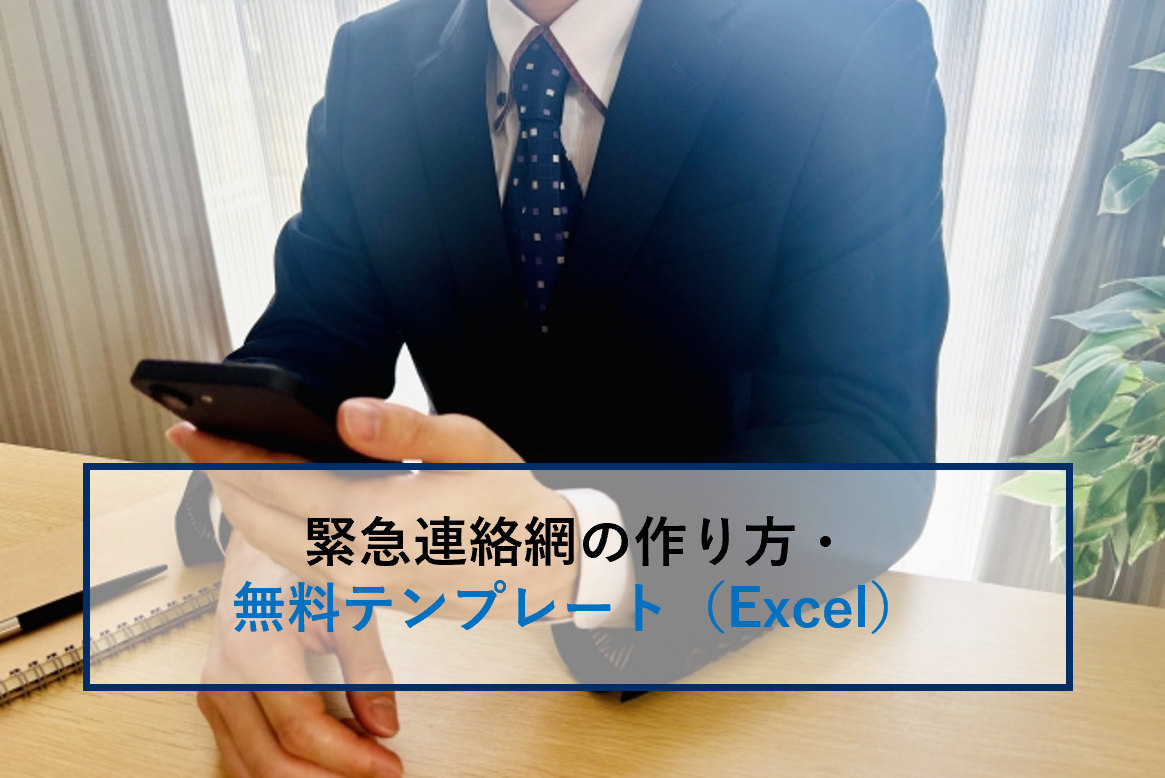緊急事態が起きたときに、従業員の安全や状況を即座に確認するのに役立つ安否確認システム。この記事では数多ある安否確認システムの中から、自社に合う安否確認システムを選ぶ方法を解説します。
あわせておすすめの安否確認システムを10製品ご紹介します。機能や価格、実績などをまとめましたので、安否確認システムの選定にお役立てください。
安否確認システムの基本機能
安否確認システムには一般的に以下の機能が搭載されています。
- 安否確認メッセージの一斉配信機能
- 気象庁の情報と連動した自動送信機能
- 未回答者に対しての再連絡
- 回答の自動集計・分析機能
- チャットや掲示板機能
- 従業員の家族への安否確認機能
安否確認システムによって利用できる機能が異なるため、自社で使いやすいシステムを導入するには機能をよく比較することが重要です。
安否確認システム比較表・おすすめ10選
エマージェンシーコール|インフォコム株式会社

1995年から提供を開始し、東日本大震災でも安定稼働した信頼性。5,200社・540万IDの導入実績を誇る安否確認システムがエマージェンシーコールです。気象庁の情報と連動した自動送信機能に加え、メール、電話音声、専用アプリ、LINE(※オプション)など多彩な連絡手段へ最大100回自動で再送信し、担当者の負担軽減をしつつ圧倒的な回答率を実現します。安否回答状況を確認できる管理者IDは無制限のため、拠点数の多い大企業でも柔軟な運用が可能です。また、従業員300名以下の企業様には1万円から始められるライトプランもご用意しております。導入前から運用まで続く手厚いサポート体制も万全です。
BCP策定支援や無料セミナーもご提供し、安否確認に留まらず、事業継続対策を強化したい企業様に最適です。
Biz安否確認/一斉通報|NTTコミュニケーションズ株式会社

システム基盤からネットワーク回線、保守運用まですべてNTTコミュニケーションズが手がけ、信頼性の高さを重視している安否確認システムです。震度7の地震にも耐えうるデータセンターを完備しており、安定稼働を実現しています。
気象庁の速報と連動した自動送信機能や集計機能、未回答者へのリトライ機能など基本的な機能が揃っています。操作に困ったときやトラブル発生時には、24時間対応のヘルプデスクに無料で相談できるのも魅力です。
セコム安否確認サービス|セコムトラストシステムズ株式会社

日本初の警備保障会社・セコムによる安否確認システムで、これまでセキュリティ事業で培ってきたノウハウをもとに開発されました。トラストオペレーションセンターが常に災害情報の収集や精査を行う、機械任せでないサポート体制が特徴。より精度の高い情報を届け、災害時の初動対応を強力にサポートします。
そのほかメールアドレスが存在しているかを確認するクリーニング機能や、GPSの位置情報通知機能など担当者をバックアップする体制が整っています。
ALSOK安否確認サービス|綜合警備保障株式会社

地震発生時の自動発信機能や未回答者への自動リトライ機能、掲示板などひと通りの機能が揃うALSOK安否確認サービス。地震や津波の情報、注意報・警報などの情報配信サービスの機能も付いているため、災害情報をいち早く拡散できます。
掲示板が複数作成できるのも特徴のひとつ。部署ごとに作成できるほか、従業員とその家族のみの掲示板も作れるため、情報共有や安否確認がスムーズに行えます。45日間の無料トライアルを経て本格導入できる点も魅力です。
安否確認システム ANPIC(アンピック)|株式会社アバンセシステム

ANPIC(アンピック)は、株式会社アバンセシステムが静岡県の大学とともに開発しました。直感的に操作できるインターフェイスに自信を持っており、特に国立大学でのシェア率が高いシステムです。
自動配信のための地震の震度設定は、都道府県や地方ごとに細かく設定できるため、複数の事業所がある企業でも使いやすくなっています。初期登録の無料代行サービスや初回無料の導入説明会、専任の担当者付きなど、サポート体制も充実しています。
安否コール|株式会社アドテクニカ

グッドデザイン賞の受賞実績のある安否コールは、端末認証の技術を用いてサーバーと紐づけるため、IDやパスワードの入力が不要な点が特徴です。登録につまずく心配が少なく、初めて安否確認システムを利用する企業にも導入しやすい使い勝手の良いシステムといえます。
さらに中小企業、大規模向けにそれぞれプランが細かく用意されているので、自社に合ったプランの選定が可能です。無料トライアル版では1ヶ月間限定ですべての機能が利用できます。
安否確認サービス2|トヨクモ株式会社

トヨクモ株式会社が提供する安否確認サービス2では、価格と機能が異なる4つのプランが用意されています。手動で安否確認を行う低価格のライトプランのほか、掲示板に写真とファイルを添付できる機能や、人事情報システムなどとの連携機能など、用途によってプランが選べます。
トヨクモ主導で、導入企業に対して一斉に行われる安否確認訓練が特徴のひとつ。上記を定期的に実施し、サーバーへの負荷訓練を行っているため、緊急時での安定稼働に期待できます。
安否確認システム e安否|株式会社ラビックス

メールと掲示板に特化した安否確認システム e安否。従業員からの回答に合わせて位置情報を取得できる機能が特徴的です。また、地盤の強い北海道石狩にサーバーを設置し、緊急時でも安心して稼働できるシステムとして自信を持っています。
プランはライトとプロの2種類で、プロプランは気象庁の速報と連動した自動配信機能や掲示板機能が利用できます。ライトプランは20名までなら無料で利用できるため、小規模企業にもおすすめです。
ANPiS(アンピス)|関西電力株式会社

関西電力株式会社のANPiS(アンピス)は初期費用がかからず、人数で変動する月額料金のみのシンプルな料金体系です。
ひと通りの機能が揃うなか、とりわけ特徴的なのは気象庁の速報と連動した自動送信機能。緊急地震速報だけでなく、津波警報や特別警報(大雨)とも自動連携しており、災害発生後30分以内に自動で安否確認メールが送信されます。自然災害のリスクが高い企業にとっては非常に使いやすい安否確認システムといえるでしょう。
安否LifeMail|株式会社コム・アンド・コム

安否LifeMailは、2000年当初から安否確認システムの開発を行ってきた株式会社コム・アンド・コムが提供するサービスです。携帯電話(スマホとガラケー)に加え、標準機能としてLINE連携が備わっているのが強みといえます。
「初期費用(150,000円)+月額費用(1人あたり80円)」というリーズナブルな価格設定も魅力。「初めて安否確認システムを導入するので費用を抑えたい」と考える企業にもぴったりのシステムです。
自社に合う安否確認システムの選び方のポイント
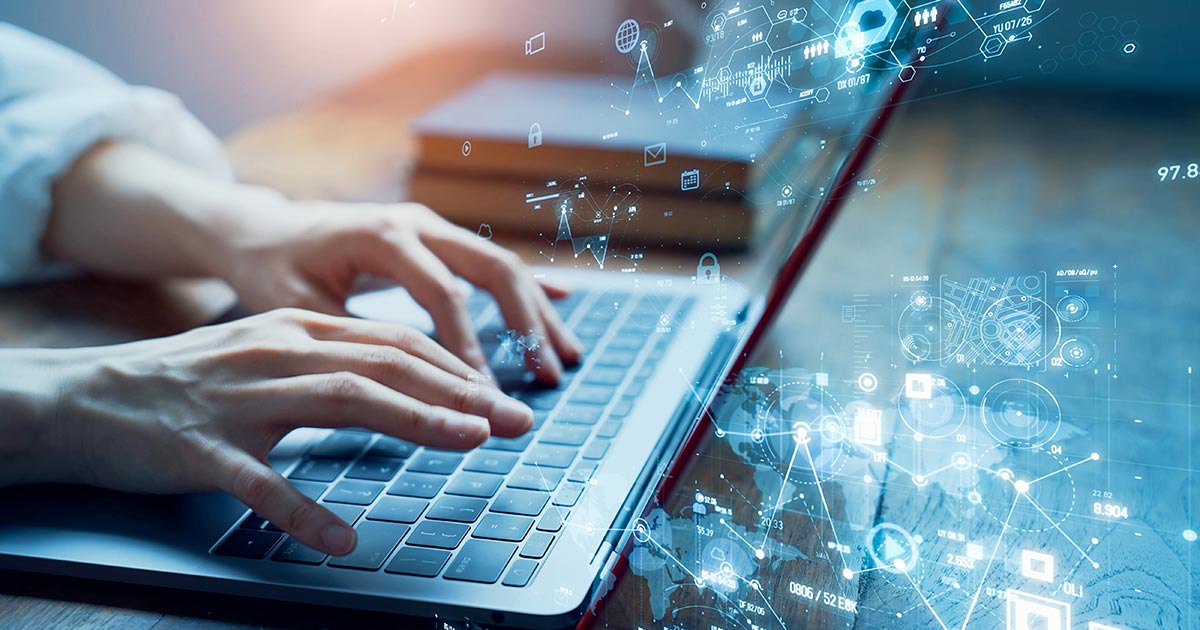
最後に、自社に合う安否確認システムを選ぶポイントを3つ紹介します。
1)実績が豊富か
まずは導入社数やサービスの提供年数などの実績をチェックしましょう。導入者数は満足度の高さや評判の良さ、提供年数は豊富な経験と実績を表しているため、システム選びの判断材料になります。
これまで起きた自然災害の際に、問題なく稼働していたかも大きなチェックポイントです。たとえば東日本大震災や熊本地震の際に停止せずに稼働した実績のあるシステムは、これからのBCP対策の心強いパートナーになってくれると考えられるでしょう。あわせてデータセンターが複数あるかもチェックしておくと安心です。
2)複数の連絡手段があるか
安否確認システムによって、利用できる連絡手段の種類が異なります。たとえばメールだけで安否確認を行うシステムや、専用アプリも利用できるシステムなど、その特徴はさまざまです。
複数の連絡手段が利用できるシステムだと、従業員がメールを使えない状況にあった場合、違う手段を使えるため回答率がぐっと高まります。メールだけでなく、電話の音声や専用アプリ、LINEなど複数の連絡手段が利用できるシステムをぜひ検討してください。
3)繰り返し連絡があるか
従業員からの回答率を高めるには、自動のリマインド機能が非常に重要です。未回答の従業員に対し、繰り返し自動的に発信する機能があると、災害時に担当者が未回答者を追いかける手間も減ります。
しかし従業員がメールで回答できない状況下にあるのに、同じ手段で連絡をとっていてはスムーズに安否確認ができない可能性が高まります。複数の連絡手段でリマインドできる機能があるかも重要なチェックポイントです。