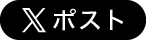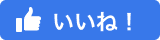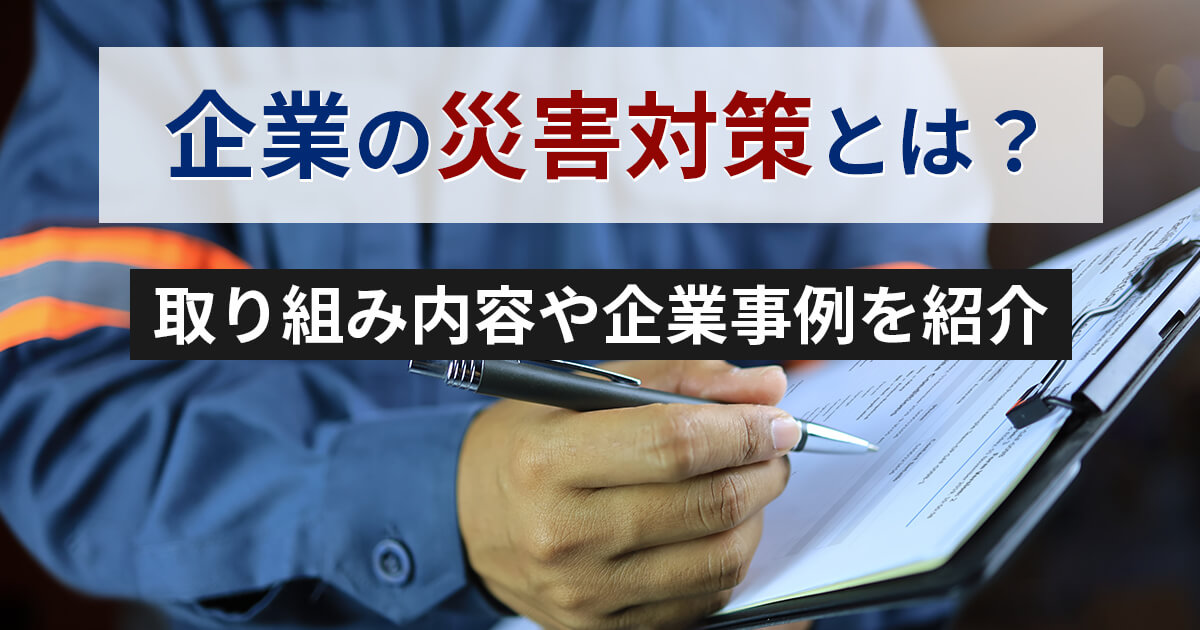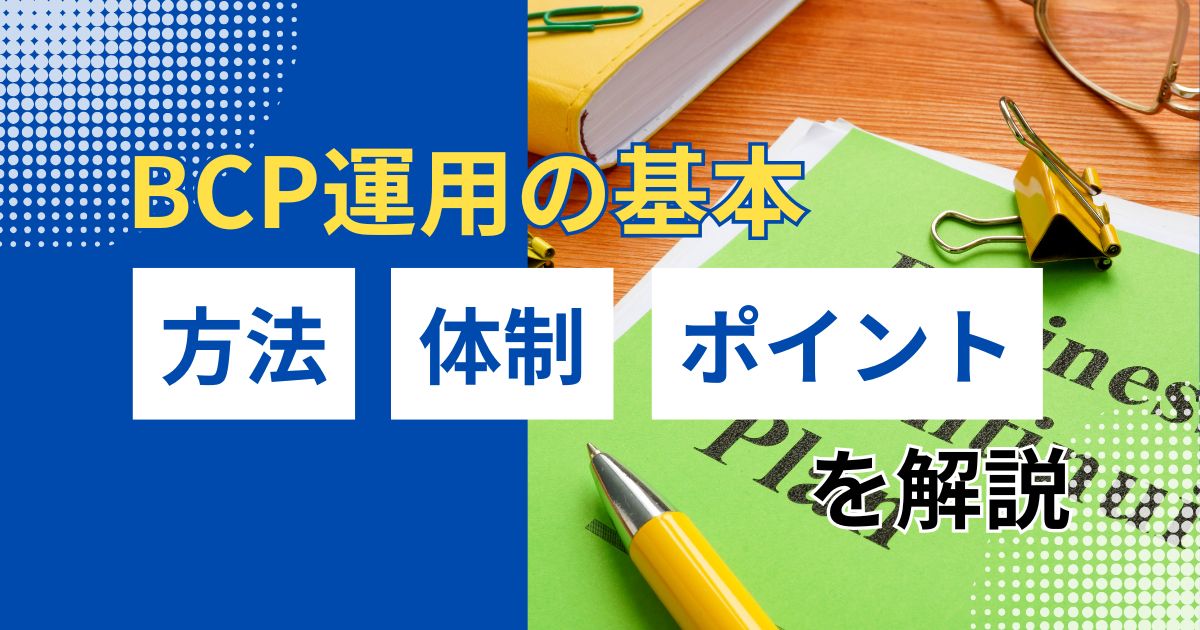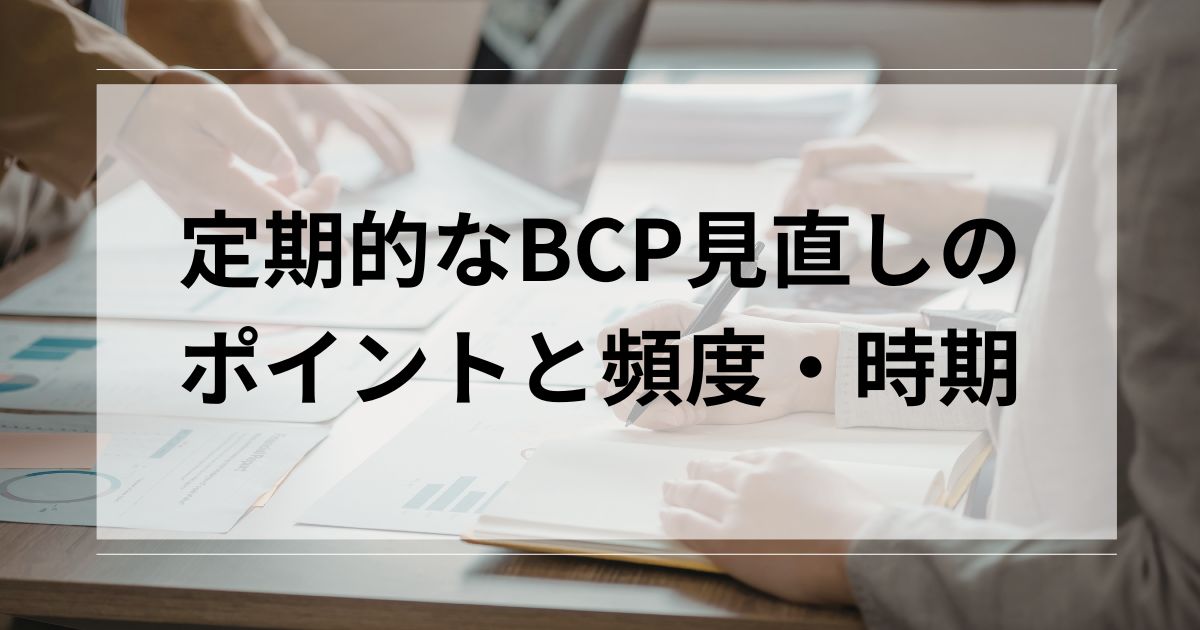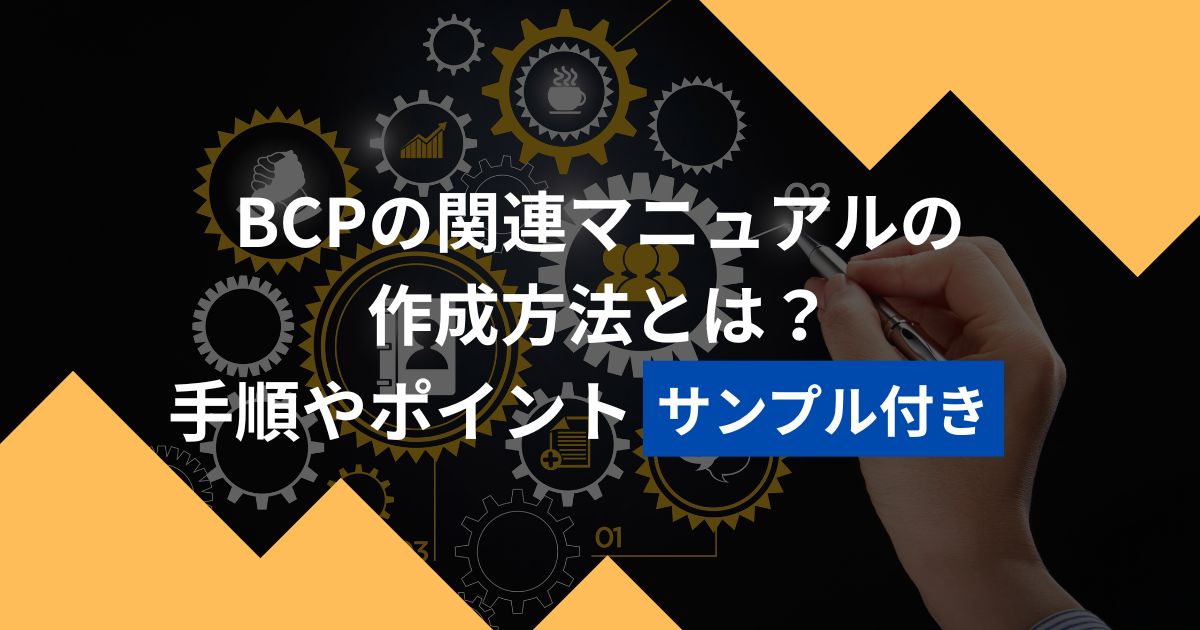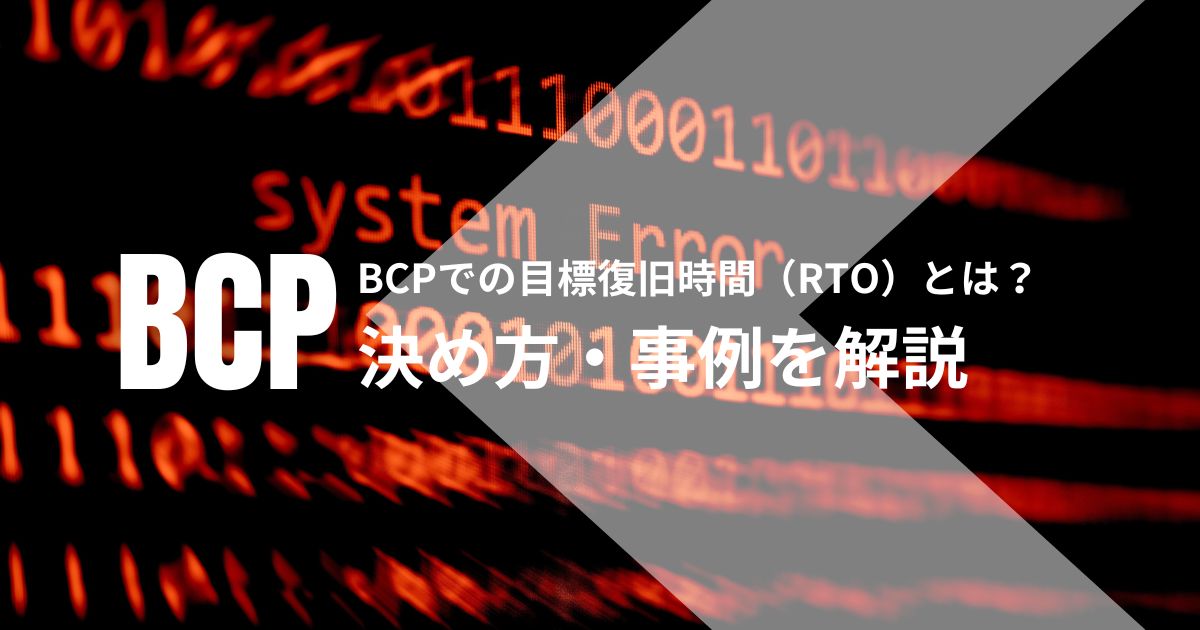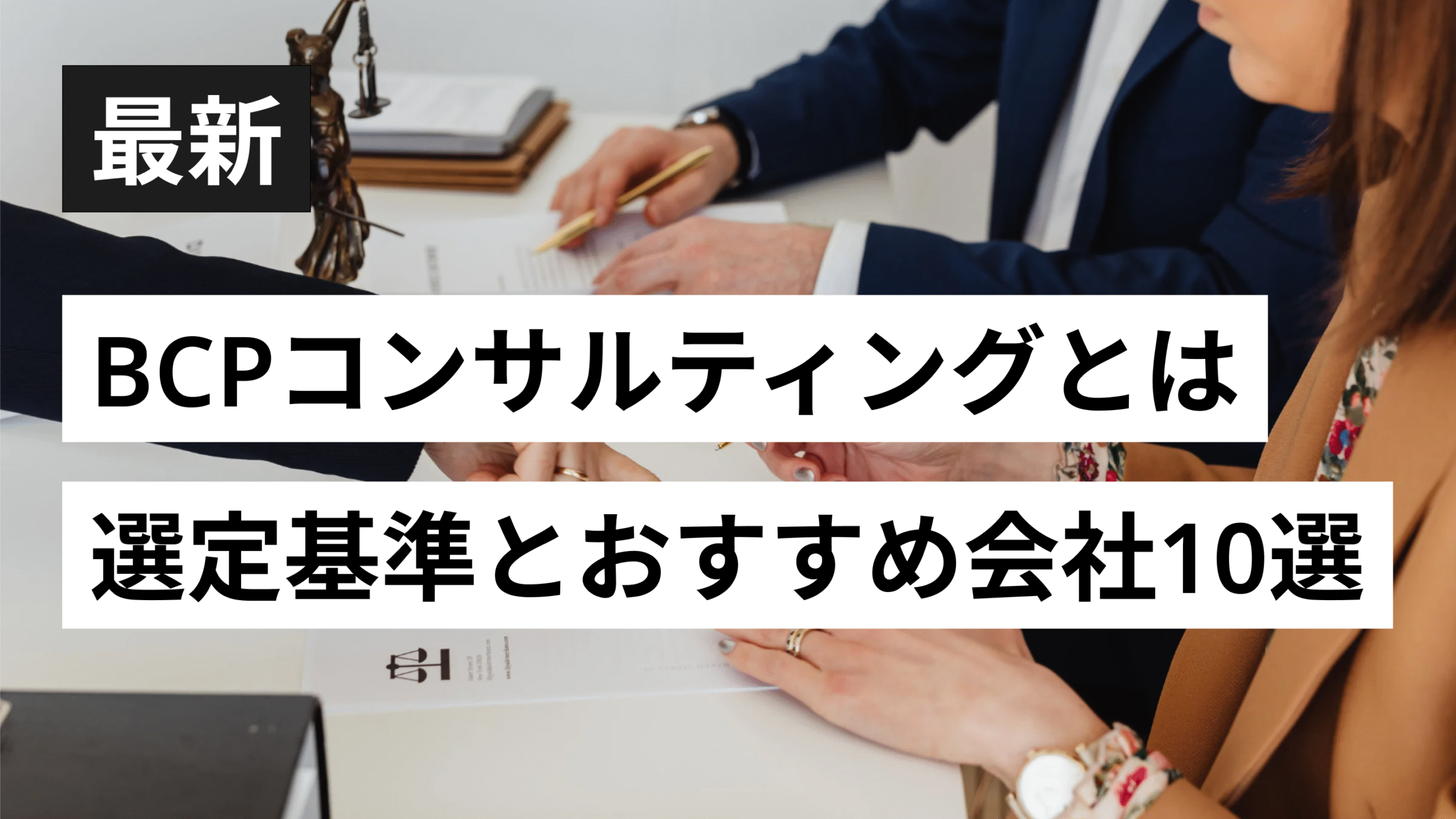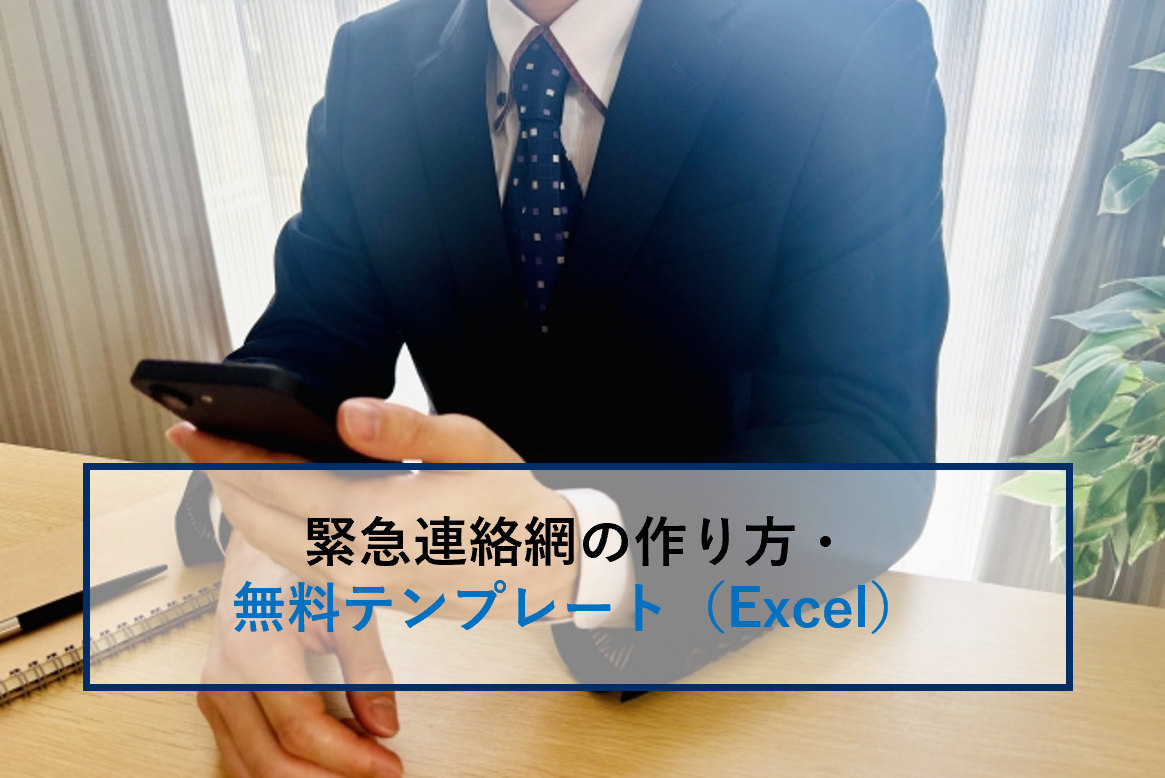目次
日本は地震や洪水、台風などさまざまな自然災害が発生するリスクの高い国です。そのため災害対策が重視されており、大手企業だけでなく、中小企業においても災害に備えた取り組みが求められています。
この記事では防災体制を強化したい企業に向けて、具体的な災害対策を紹介します。他企業の災害対策の事例も紹介しているので、取り組みの参考にしてみてください。
企業の災害対策とは
企業の災害対策とは、自然災害に備えて行う事前対策を指します。災害対策は大きく「防災」と「事業継続」の2つに分けられ、以下のような違いがあります。
| 防災対策 | 地震や津波などの災害による人的被害および物的被害を最小限に抑えるための対策。建物や設備の補強、備蓄の準備、防災訓練などの対策が該当する。 |
|---|---|
| 事業継続対策 | 事業の継続、または早期復旧に重きを置いた対策で、事前にBCP(事業継続計画)を立てて緊急事態に備える。BCPは自然災害だけでなくパンデミックやシステム障害など対象の幅広さが特徴。 |
自然災害対策など具体的な企業の取り組み

自然災害リスクを始めとして、事前の対策は非常に重要です。この章では企業ですぐに取り組める防災対策などの取り組みを紹介します。
オフィスや工場の耐震・耐水対策
ハザードマップを確認したうえで、起きやすい災害に向けた対策を行いましょう。たとえば洪水や津波などの被害が予想される場合は、浸水リスクの少ない場所へ設備や備蓄を移動するなどの方法が考えられます。止水板を使った浸水対策も効果的です。
地震災害に対しては、家具や設備の転倒防止対策を行いましょう。現在、大規模な地震の発生リスクが高い地域以外でも、いつどこで地震が発生するかわからないため、どの地域においても地震対策は必要です。パソコンを机に固定する、重い物を高い位置に設置しないなど、手軽に行える対策もあるため、できる取り組みから始めましょう。
防災備蓄の準備と管理
内閣府のガイドラインでは、帰宅困難者を想定して3日分以上の備蓄の用意が望ましいと考えられています。以下のリストを参考に用意してみましょう。
- 飲料水(1人あたり計9L以上)
- レトルト食品などの非常食(1人あたり計9食以上)
- 毛布(1人1枚ずつ)
- 簡易トイレやトイレットペーパー
- 敷物
- 懐中電灯
- ラジオ
- 手回し充電器や乾電池など
- 救急用品
そのほか、以下の防災備蓄用品も役に立ちます。
- ウェットティッシュ
- カセットコンロ
- 給水用のポリタンク
- 軍手
- ビニール袋
- ヘルメット
防災マニュアルの作成
防災マニュアルとは災害時に命を守るための行動指針や、従業員の役割をまとめた資料です。具体的には以下の内容を盛り込み、作成します。
- 災害時の組織体制と任務分担
- 災害発生時の情報収集の方法について
- 安否確認方法の確立
- 避難経路や避難方法の設定
まずは災害対策本部を立ち上げ、リーダーや避難誘導担当など役割分担を行いましょう。災害時に的確に行動したり、判断したりするには、正確な情報収集も欠かせません。社内外の情報をスムーズに収集する方法もあらかじめ決めておきましょう。
何より、緊急時に従業員が迷わず行動できるよう防災マニュアルは簡潔にわかりやすくまとめる必要があります。作成して完了ではなく、従業員に周知させる研修などの取り組みも非常に重要です。
防災訓練の実施
災害時に従業員が協力し合いながら行動できるよう定期的な防災訓練が必要です。たとえば地震を想定した避難訓練や火災時の消化訓練、救護訓練などを行います。救護訓練では心肺蘇生やAED、人工呼吸などの方法をすべての従業員にマスターさせられると安心です。
また、安否確認の訓練も欠かさず行いましょう。いつ、どこで、どんな規模の自然災害が起きるかわからないため、あらゆる災害や時間帯を想定したシナリオを作成し、訓練を行います。安否確認システムを利用している場合は、システムが問題なく稼働するかのチェックも重要です。
いずれの訓練も繰り返し実施し、すべての従業員が参加できるよう取り組む必要があります。訓練後は必ず内容の見直しと改善を行い、精度を高めていきましょう。
BCPの策定
上記で紹介した取り組みは、人的被害および物的被害を抑える防災対策の側面が強いため、より一歩踏み込んだ対策を行いたい企業はBCPを策定しましょう。BCPでは防災対策に加え、災害発生後の事業継続や復旧に関する対策を盛り込む必要があります。
具体的な手順としては、優先的に継続させたい中核事業を選定し、必要な対策を練ります。たとえば工場や設備が被災した場合に備えてまとまった資金を用意しておく、取引先が業務停止した場合を想定して原料の調達先を複数確保するなどの準備が必要です。
詳しくは以下の記事を参考にしてください。
企業の災害対策事例

続いて具体的な災害対策事例を3つ紹介します。
1)防災マニュアルを浸透させるため訓練をセットで(宮城/製造業)
まずは東日本大震災を契機に防災・危機管理マニュアルを強化した、宮城県の製造販売業者の事例を紹介します。同企業では現場で活用しやすいよう、派遣社員やアルバイトなどの立場別、自然災害のパターン別に防災マニュアルを分けて作成しました。
さらに現場への定着を図るため、地震津波訓練や上級救命講習、嘔吐物処理など多彩な防災訓練を年50回以上行っています。これらの取り組みにより従業員の意識が向上したほか、「人を大切にする企業」としてのイメージがつき、新卒採用にも好影響がもたらされました。
2)災害リスクや避難場所の情報を収集して独自のハザードマップを作成(徳島/建設業)
徳島県の建設事業者では地域防災を意識し、独自のハザードマップを作成しました。対策チームが周辺地域のハザードマップ情報や避難場所、社員の自宅や取引先などの情報を収集し、マップに落とし込むことで、一元管理を可能にしています。
同企業では停電した場合に備えて、データだけでなく、紙でもマップを作成。紙のマップは災害対策本部に保管し、いざというときにすぐに利用できるようにしています。
顧客の情報もマップに盛り込んでいるため、メンテナンスやリフォームの巡回ルート作成にも役立つなど、副次的な効果も生まれています。
3)水害対策として備蓄の整備と損害保険への加入を(福岡/製造業)
福岡県の製造業者は主要取引先からの要望によりBCP策定を決意し、主に台風による風水害を対象に防災対策を行いました。策定を進めるなかで水災害を補償する損害保険の対象に本社しか含まれていないことがわかり、工場や設備を追加。直後に起きた九州北部豪雨では、被害を受けた工場や設備を修理するのに十分な保険金を得られました。
あわせて備蓄の準備を念入りに行っています。水や食料のほか、復旧作業に使うデッキブラシや高圧水洗浄機などの掃除用具を準備しました。水害時に浸水しないよう備蓄を高い場所へ置くなど、保管場所も工夫しています。
企業が早急に災害対策を行うべき理由

最後に、企業が自然災害への対策を早急に行うべき理由やその必要性を2つに分けて解説します。
企業のビジョンやミッションを成し遂げるため
災害は、従業員の人命や事業の継続に関わり、企業の存続にも影響を与えます。近年、日本では自然災害の頻発・激甚化が進んでおり、いつどこで災害に巻き込まれるかわかりません。さらに政府の調査委員会は、30年以内に南海トラフ巨大地震が起こる可能性を80%に引き上げました。
こうした事態が予測されるなか、企業が安全配慮義務を果たすための災害対策が、法的な側面だけでなく、社会全体からも求められています。また、防災対策を講じることで、どんな事態でも企業の事業継続できる体制が整えられ、企業のビジョンやミッションの遂行につながっていきます。
災害対策は一朝一夕ではできないため
災害対策は思い立ってすぐに実行できるものではありません。災害発生リスクの分析から、防災マニュアルの作成、備蓄の用意など、するべきことは多岐にわたります。
また、実施すべき項目だけでなく、災害対策の計画と実施を年単位でやり切るための費用を捻出できるか、など費用面での問題もあります。さらに、防災意識を従業員に浸透させるための研修や訓練も必要です。特に災害を想定した訓練は継続的に実施し、避難や安否確認などが災害時にスムーズに行えるよう定期的な見直しが求められます。
効果的な災害対策を準備するためにも、早めの着手をおすすめします。
万が一の事態に備えて企業の災害対策を強化しよう
企業には従業員に対する安全配慮義務が課されているため、地震や洪水などの自然災害への対策が必要です。自社を脅かすリスクの高い自然災害を把握して、早急に災害対策を進めましょう。
災害時には、適切な初動対応につなげるための正確な情報収集が特に重要です。災害対策の一環として、災害の情報を素早く収集・共有できるシステム「BCPortal」と、リアルタイムで危機を管理できるシステム「Spectee Pro」の導入もぜひ検討してみてください。