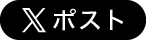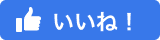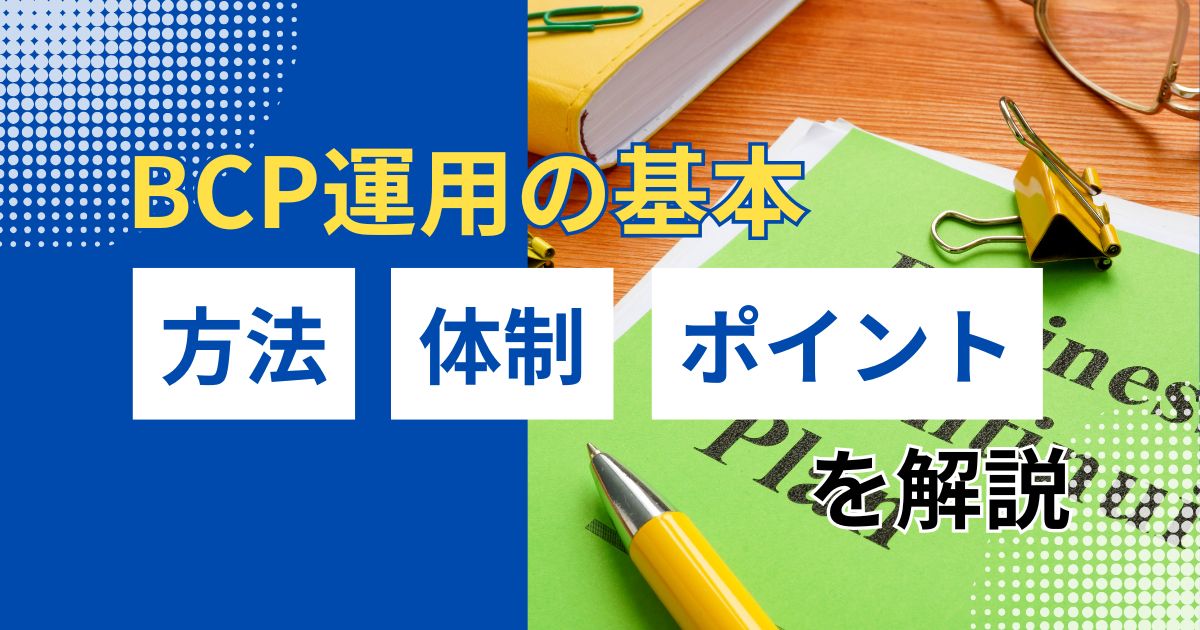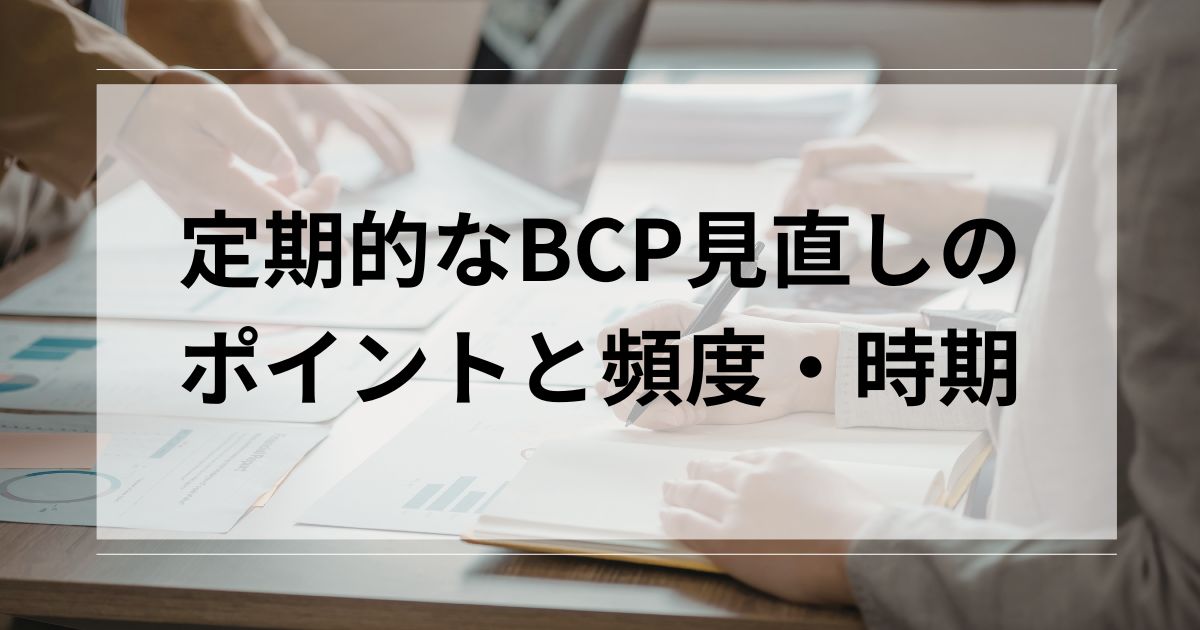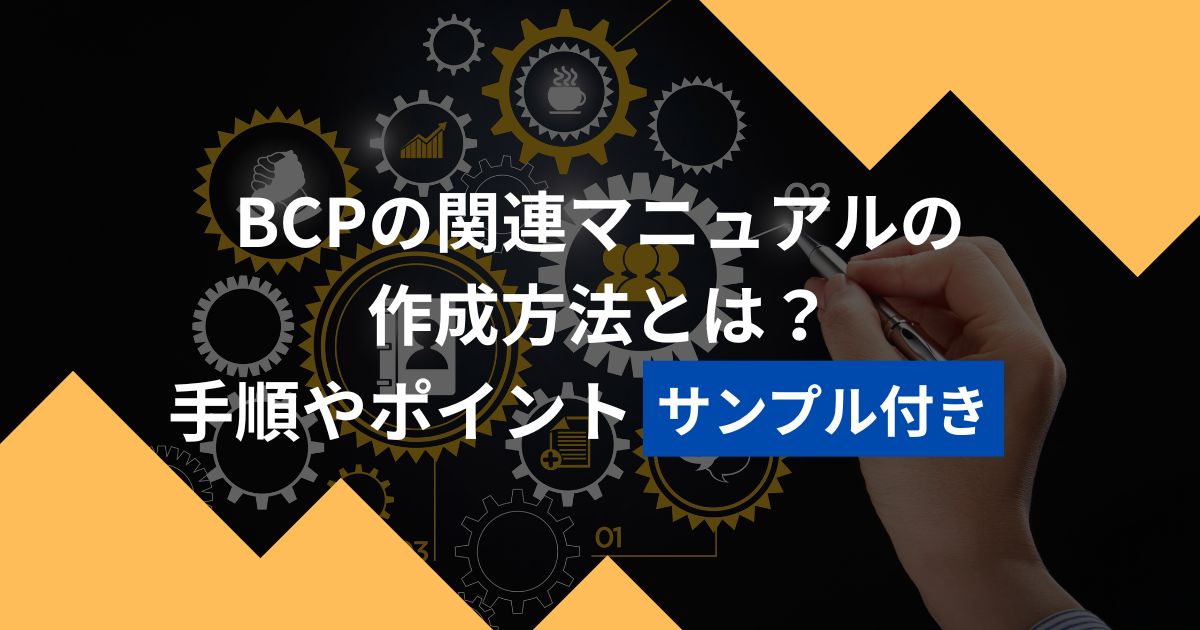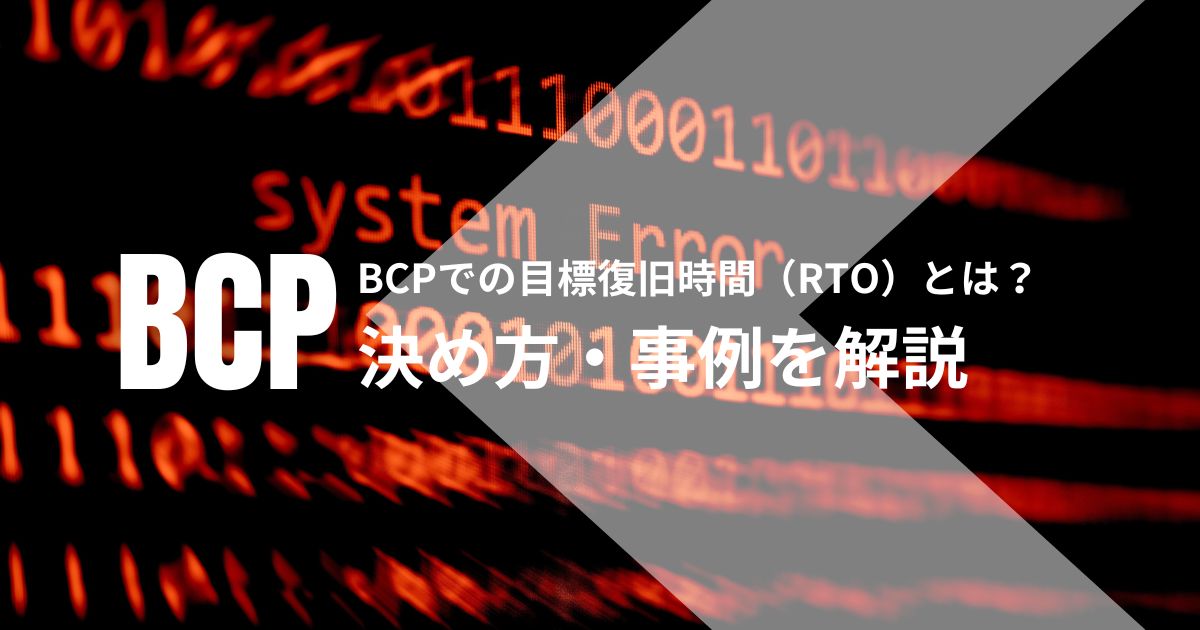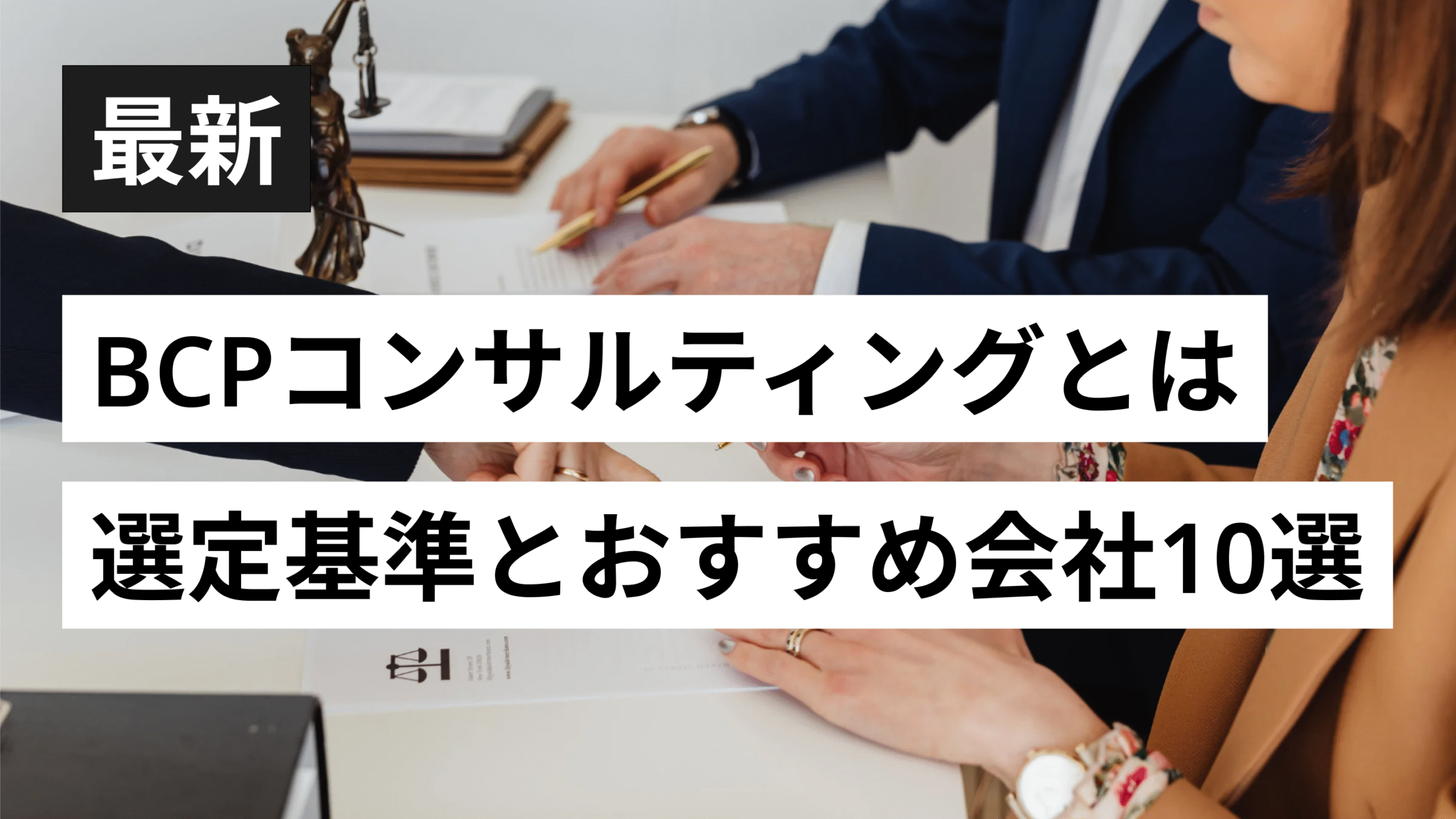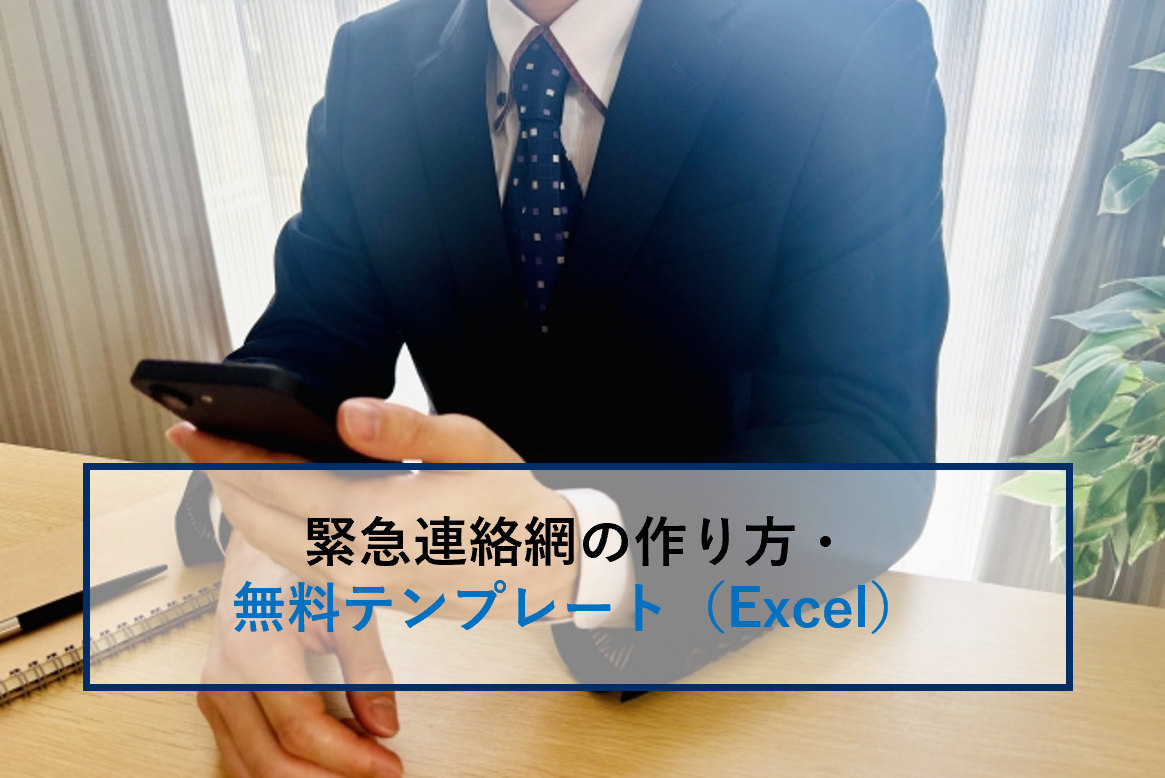目次
災害などの緊急事態で製造業の業務が滞ったり、停止したりするとサプライチェーン全体に影響を及ぼす危険性があります。そのため大企業だけでなく中小企業においてもBCPの策定が非常に重要です。BCPを事前に準備しているか否かで、事業が停止したあとの復旧スピードも異なります。
この記事では主に中小製造業(300人以下)に向けて、BCP策定の方法やポイントを詳しく解説します。製造業におけるBCPの事例もまとめました。
製造業におけるBCPとは
BCPは事業を停止させない、または早期に復旧させるための計画です。とりわけ製造業においては、災害発生で工場や設備が破損して莫大な修繕日がかかったり、生産ストップにより取引先に多大な迷惑をかけたりなど、被害が大きくなる傾向があることからBCP策定が重要視されています。また、新型コロナウイルス感染症が製造業に大きな影響を与えたように、自然災害だけでなくパンデミックへの対策も欠かせません。これらのリスクに対策するには、あらゆるインシデントへ対応するためのBCP策定が必要です。
BCPを策定している企業と、策定していない企業ではインシデントが発生してから復旧するまでにかかる時間も異なります。サプライチェーンを止めないために、大手企業だけに限らず、中小企業もBCPの策定を行いましょう。
【中小企業向け】製造業におけるBCP策定方法
BCP策定する際には、内閣府のガイドラインをもとに作成された経済産業省や厚生労働省のガイドラインが参考になります。ここでは経済産業省 中小企業庁のガイドラインを参考に、BCPの策定方法を解説します。中小企業と大手企業でBCP策定の基本プロセスに大きな違いはないため、大手企業のご担当者の方もぜひ参考にしてください。
基本方針の立案と運用体制の確保
まずはBCP策定の基本方針を立案します。基本方針とはBCPを策定する目的です。たとえば「従業員の安否確認を最優先に行うため」「早急に事業を再開しお客様の信用を守るため」など、BCPを策定するための目的を洗い出し、まとめましょう。
また、必要に応じて対策チームの設置が必要です。各部署のメンバーを集め、プロジェクトチームを立ち上げると良いでしょう。小規模な企業の場合はチームを立ち上げず、まずは経営者1人でBCPを策定する方法でも構いません。
事業を脅かすリスクの把握
続いて、自社で対策を行いたい発生リスクの高いインシデントを洗い出します。大雨や洪水、感染症など自社を脅かすリスクを具体的に挙げ、どのような被害が起きるかイメージしましょう。なお、地震大国といわれる日本はどの地域においても、大規模な地震が発生する危険性があります。そのため、どの企業においても地震への対策は必須です。
あわせて自社にとって優先的に継続させたい中核事業の分析も行いましょう。中核事業とは停止した場合、経営状態に大きな影響を与える事業をイメージして選びます。
事前対策の実施
上記で洗い出したリスクに対し、事前に行える対策を考えます。たとえば備蓄の整理、商品や防災グッズの保管場所の検討、データの格納場所の分散、近隣企業との連携などが考えられます。
製造業においてはサプライチェーンを停止させないために、原料の仕入れ先に関して代替案を用意したり、工場内の機械が倒れたりしないよう固定したりなどの対策が必要です。
緊急時の対応を計画
自然災害やパンデミックが発生した際の対応を計画します。具体的にはBCPの発動条件や初動対応のフロー、事業継続のための体制を決めます。初動対応としては従業員やその家族の安否確認、情報収集や状況の把握、二次災害を防止するための措置などが考えられます。
また、事業継続がスムーズに行えるよう責任者の選出が必要です。小規模の事業所の場合は、経営者がリーダーシップを取る方法でも構いません。責任者や経営者が被災した場合に備えて代理の責任者も選出してください。
製造業におけるBCP策定のポイント
次に、製造業におけるBCP策定のポイントを4つ解説します。
工場や設備の安全対策を実施
工場や設備が被災すると、事業の継続に大きな影響を与えるため、事前の安全対策が必須です。たとえば地震に備えて設備などが倒れないよう固定したり、建物の耐震強度を見直したりなどの方法が考えられます。洪水リスクの高い地域では、止水板を設置するなどの浸水対策を講じましょう。
いずれの場合も万一の事態を考え、代替の工場や設備の準備が必要です。自社事業が停止した場合に備えて、他地域の同業他社と連携し、いざというときに助け合える体制を整えておくとより良いでしょう。
安否確認の方法を整備
緊急事態が発生した際は、初動対応のひとつである従業員の安否確認がもっとも重要です。安否確認を迅速に行うことで、その後の初動対応がスムーズに行えます。
安否確認を素早く適切に行うために、その方法を検討し、体制を整備しておきましょう。従業員の安否確認はメールや電話などさまざまな方法があります。従業員の多い企業では担当者の負担を減らすために、実績の豊富な安否確認システムを導入する方法がおすすめです。安否確認システムには、メールの一斉配信や回答の自動分析などさまざまな機能が備わっています。
緊急時の資金確保
事業が停止した場合や、設備・工場が被災した場合に備えて、すぐに利用できる資金を確保しておきましょう。災害時に必要な資金を算出するには、経済産業省関東経済産業局で配布している「リスクファイナンス判断シート」が参考になります。
あわせて保険の見直しを行ってください。自社のリスクに対し、損害補償の内容が適切であるか必ず確認しましょう。
現場へのBCP浸透・定着
緊急事態下でBCPを活用するには策定だけでは不十分です。BCPの実効性を高めるため、従業員へ浸透させる研修や訓練などを必ず行いましょう。たとえば研修では、BCPの重要性を従業員に理解してもらうための勉強会や「防災」をテーマにしたグループディスカッションを実施します。心肺蘇生法やAEDの使い方を習得させるための講習も重要です。
訓練は実際に緊急事態が発生した場合を想定して、安否確認の訓練や防災訓練などを実施しましょう。訓練を実施したあとは必ず見直しを行い、緊急事態でBCPが有効に機能するよう内容のアップデートを行ってください。
製造業におけるBCPの事例
最後に、製造業で実際に行われているBCP対策の事例を3つ紹介します。自社のBCP策定をする際の参考にしてください。
事例①工場・拠点ごとにBCPを策定し取引先の信頼度アップ(鹿児島県/金属加工業)
鹿児島県にある金属加工業者は取引先の企業からBCP策定を求められたことをきっかけに、代表取締役社長がリーダーシップをとり、策定に取り組みました。管理本部と6カ所の工場で立地条件が異なるため、ハザードマップや災害情報をそれぞれ収集したうえで、現場ごとにBCPを策定しました。
きめ細かな対応が企業の信用向上つながり、取引先との関係が良好になったといいます。また、この取り組みが経済産業省 九州経済産業局の事例集へ掲載されたことにより大手企業からの問い合わせにつながり、新たな取引関係を構築できました。
事例②水害対策として止水板の設置や納品物の保管場所の変更を(福岡県/看板・標識製造業)
福岡県のある製造業者はこれまで三度も大雨の浸水被害に合い、補助金を使った水害対策を決意しました。この補助金の申請条件にBCPの策定が含まれていたため、防災対策だけでなく事業継続に向けた計画の策定に着手しました。
自社の状況を分析したうえで、事前対策として高額かつ生産に重要な設備の周りにのみ止水板を設置。さらに排水機能を強化して、万が一床下浸水した際に水がたまらないような対策を講じました。また、納品物や作業道具などを普段から高い場所へ保管するよう従業員に意識づけを行い、現在も継続しています。
事例③事業が停止した場合に備えて原材料仕入れ先の代替案を(福岡県/食料品製造業)
福岡県の老舗和菓子メーカーは西日本豪雨を経験し、BCPの策定が急務と考えました。まずはサプライチェーンリスクを低減させるため、原材料の仕入れから梱包に至るまで、それぞれ2社ずつ発注先を確保しました。
さらに水害対策だけでなく感染症対策も必要と考え、人員不足を防止するために店舗間での連携を強化。店舗ごとのオペレーションを整備し、従業員に定着させるための研修を定期的に実施しました。BCP策定により、業務停止リスクが軽減され、取引先からの信頼向上にもつながったといいます。
製造業においてBCPの策定は必須
大手企業や中小企業に限らず、製造業においてBCPの策定は非常に重要です。BCP策定により、サプライチェーンを停止するリスクを大幅に軽減できるうえ、被災したあとの事業の早期復旧にもつなげられます。まだBCPを策定していない製造業者は早急に対策を進めましょう。
BCP対策のひとつとして、緊急時の情報をいかにスムーズに正確に収集できるかも鍵です。災害に関する情報を素早く収集・分析し、初動対応につなげるシステム「BCPortal」や、リスクを可視化して危機を予測するシステム「Spectee Pro」にもぜひ注目してみてください。