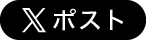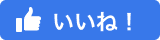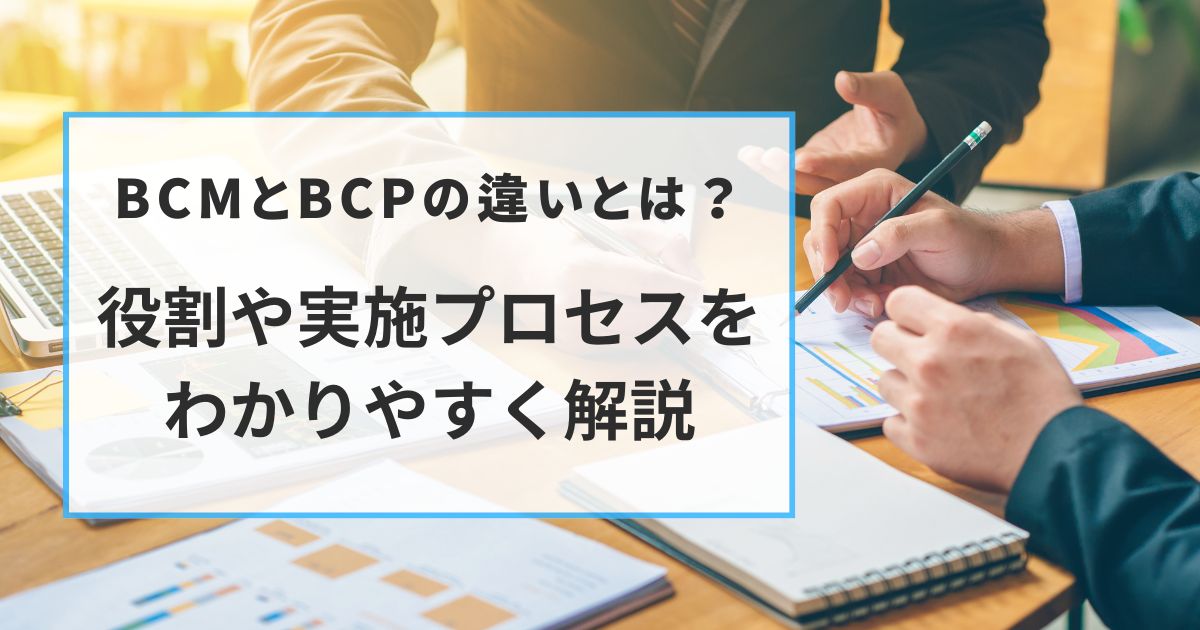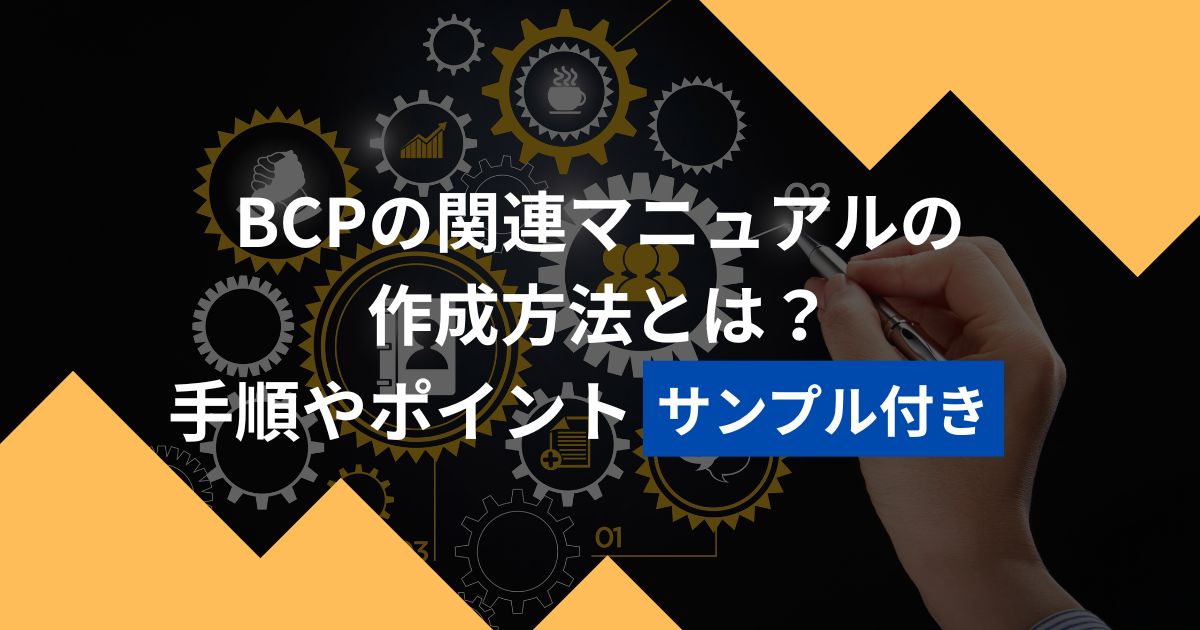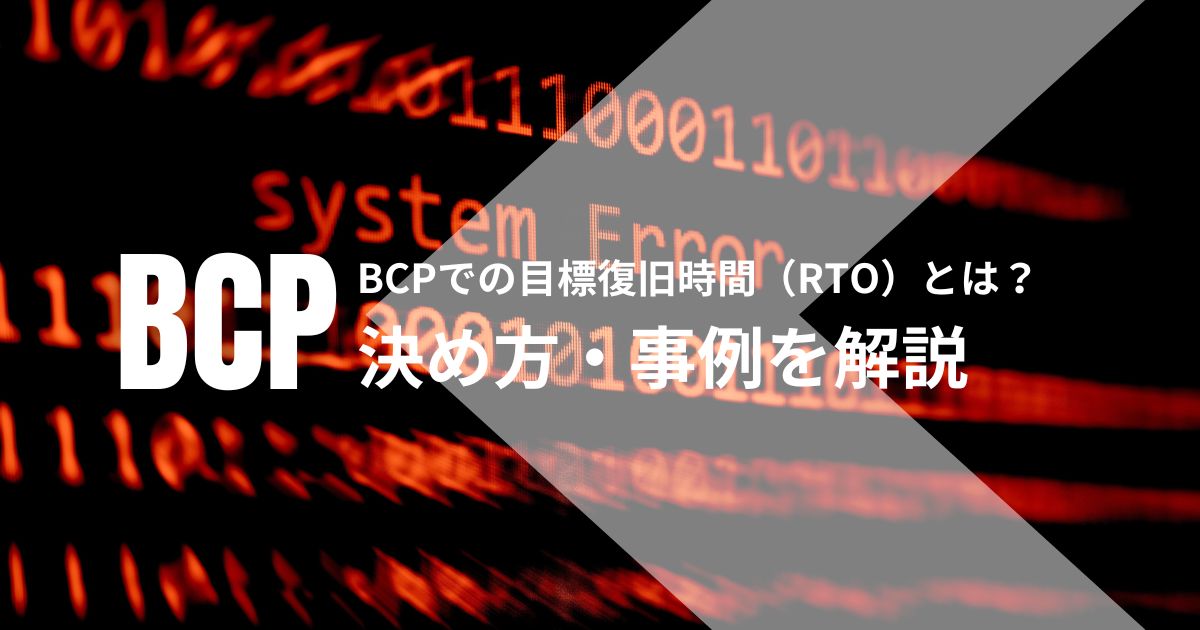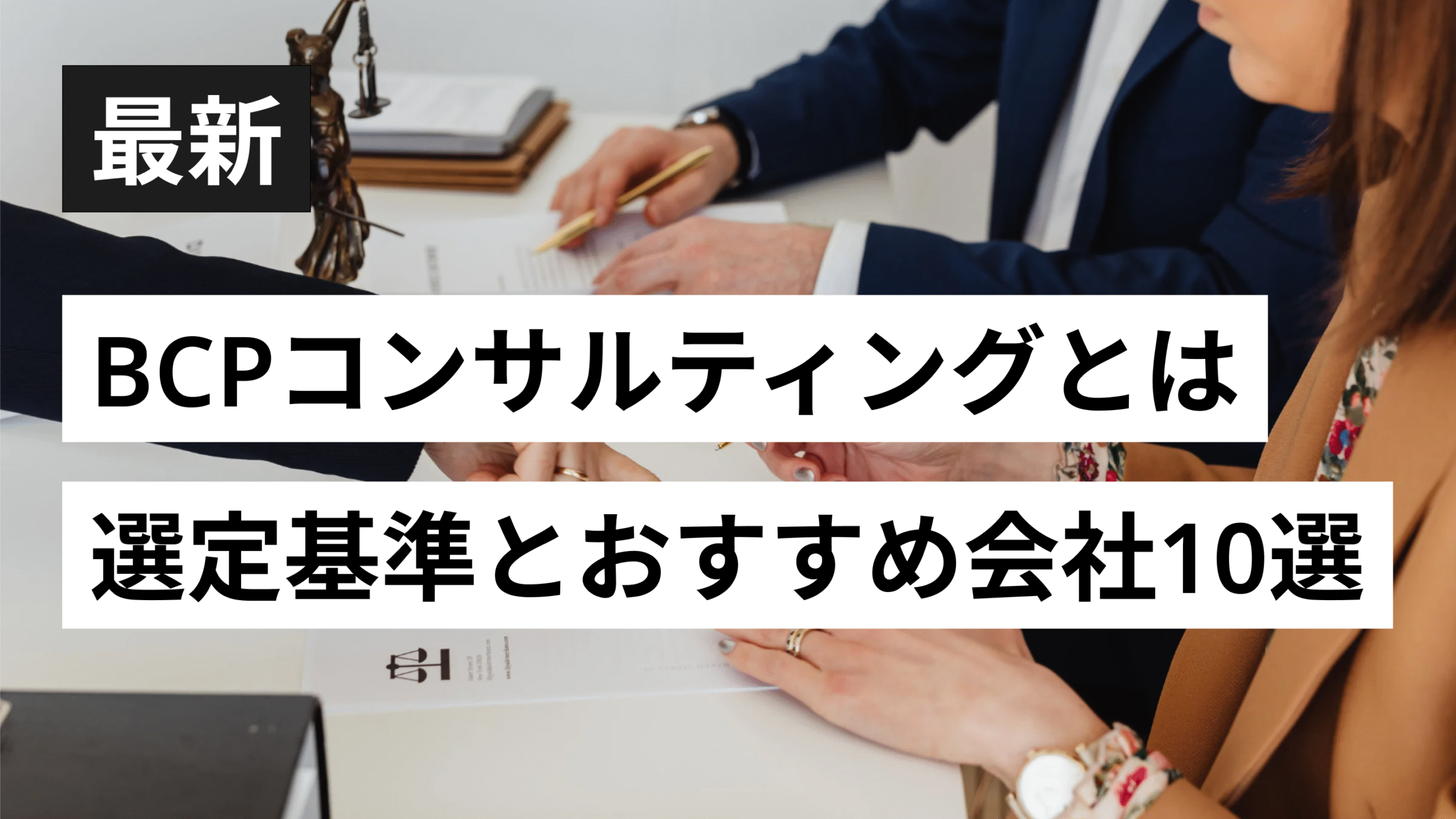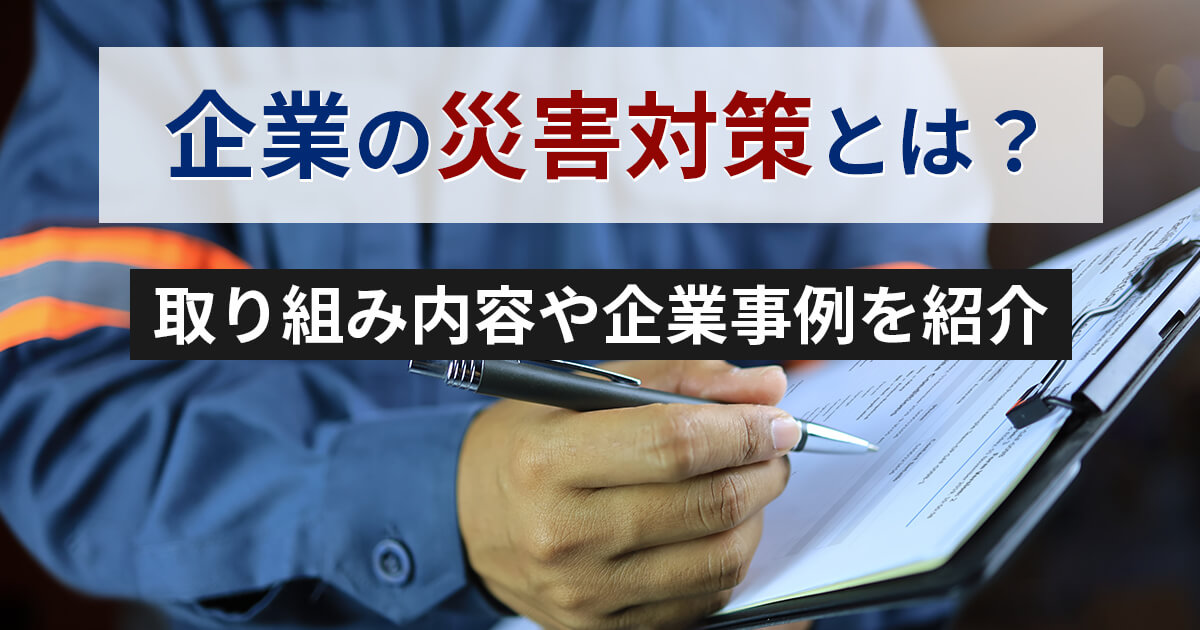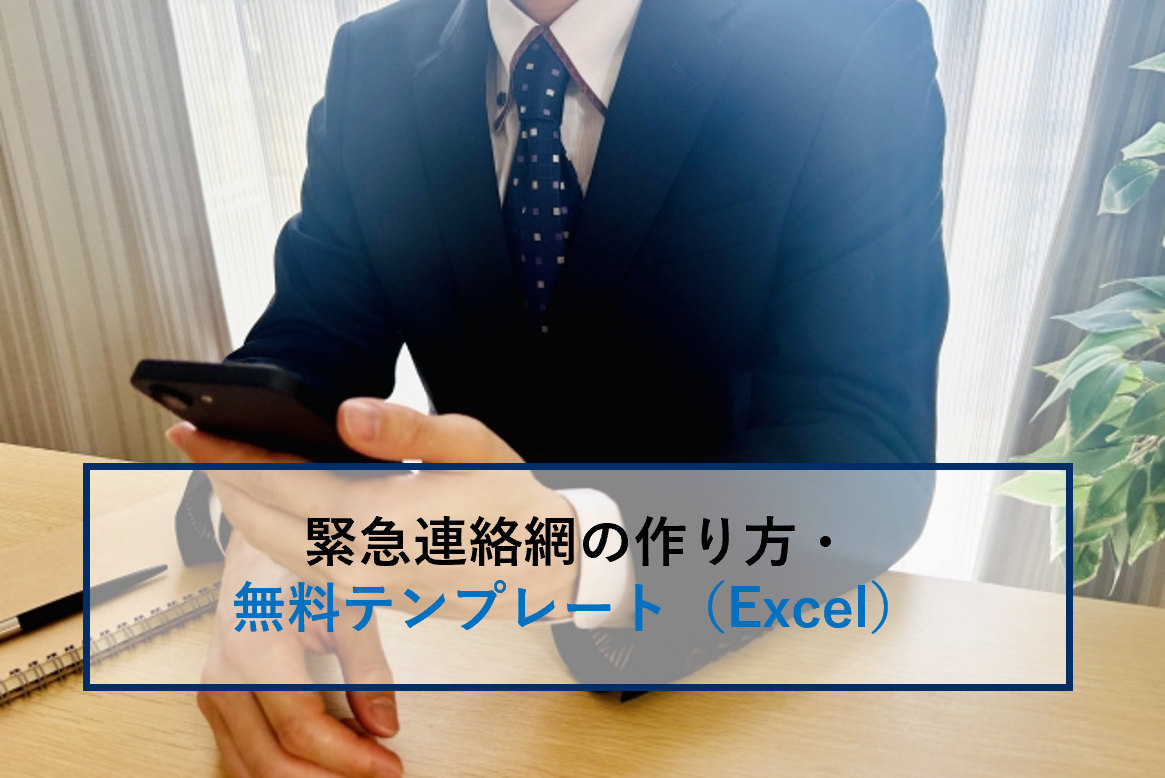目次
災害やパンデミックなど緊急事態が発生した際に、事業を継続させるにはBCP(事業継続計画)の策定が重要です。その際、BCM(事業継続マネジメント)も一緒に構築することで、より災害への対応力を高められます。
この記事ではBCMとBCPの違いから重要性までわかりやすく解説します。BCMを実施するプロセスやポイントのほか、BCMS(事業継続マネジメントシステム)との違いについても詳しくまとめました。
BCMとBCPの違い
BCP(Business Continuity Plan)は事業継続計画のことで、緊急時に企業存続のために重要な事業を停止させない、停止しても迅速に再開するための計画をまとめた文書を指します。一方、BCM(Business Continuity Management)は事業継続マネジメントのことです。BCPを策定・運用するための一連の流れを指し、BCPの実効性を高めるにはBCMの構築がまず重要となります。
以下にBCMとBCPの違いをまとめたので、こちらの表も参考にしてみてください。
| BCM | BCP | |
|---|---|---|
| 日本語名 | 事業継続マネジメント (Business Continuity Managementの略称) | 事業継続計画 (Business Continuity Planの略称) |
| 定義 | BCPを運用・管理する継続的なマネジメント活動全体を指す。 | 緊急時に備えて、具体的な手順や対策をまとめた計画書のこと。 |
| 目的・役割 | 緊急時の事業継続を戦略的に進めるために行う。BCPの実効性を高める役割がある。 | 緊急時に重要業務を継続、または早期復旧させるために計画する。 |
| 内容 | BCPの策定・実行・見直し・改善などのプロセスで実施される。BCMを実行するための予算・リソースの確保なども活動に含まれる。 | 基本方針やBCPの運用体制・発動フロー、優先すべき重要業務と復旧目標、事前対策などの計画を文書としてまとめる。 |
BCMとBCPの関連性
BCPを策定する場合は、BCMの構築から考え、戦略的に取り組むことが求められます。BCMとBCPの関連性について以下で説明します。
BCPを支えるのがBCMの活動
BCPは策定するだけでは事業継続を実現できません。BCPの有効性を高めるには、計画に記載されている事業継続戦略実行のための事前準備や、教育・訓練などを行い、緊急時への備えを強化する必要があります。BCMを構築することで、社内にBCPを根付かせることができ、緊急時の事業継続をより強力に支えてくれます。
BCMによってBCPの継続的なアップデートが可能
BCPの改善もBCMの重要な役割です。事前準備や教育・訓練などの取り組みで気づいた問題点や不足点をもとにBCPを改善することで、自社の状況を踏まえた現実的なBCPへと育てられます。
BCPを策定したあとは、実行・見直し・改善といったBCMを構築して、この活動サイクルを回し続けることが必要不可欠です。
BCP・BCMの実施プロセスとポイント

中小企業庁の「BCP策定運用指針」をもとにBCPの策定から、BCM運用までの実施プロセスとポイントを解説します。
【1】BCPの策定
まず、BCP策定は以下の手順で行います。
それぞれのプロセスについて、以下で詳しく説明します。
①基本方針の立案
まずは経営層が中心となり、基本方針を定めます。基本方針とは事業継続を行う目的や達成すべき目標のことで、BCPの基礎となるものです。たとえば「従業員の人命を守るため」「顧客との信頼関係を維持するため」など、何のためにBCPを策定するのかを明確にしてください。
②重要業務の選定
緊急時には人員や設備などの経営資源が限られます。そのため、次の段階では優先して事業継続を行いたい重要業務の選定を行います。優先順位を決める際は、事業が停止した場合の影響度で判断するとよいでしょう。事業が停止した際、自社の売上や顧客にどれだけ影響があるかを考えてみてください。
③被害状況の確認
地震や台風などの自然災害、火災や事故、感染症のまん延、システム障害など企業の事業継続を脅かす発生事象(インシデント)は多岐に渡ります。BCPを策定するには、これらの事象で自社にどのような被害が及ぼされるかを具体的に想定し、それぞれ対策を練っていくことが必要です。
まずは震度5以上の大規模地震が発生した場合を想定し、自社の建物や設備、従業員、資金、ライフラインなどへの影響を考えてみましょう。
④事前対策の実施
上記の被害状況を想定するなかで、重要業務を継続するにあたってボトルネックとなる要素が見えてくると思います。このように重要業務の継続を妨げる、自社の弱みとなる部分を洗い出し、事前対策を考えましょう。
たとえば生産設備の地震対策が不十分な場合はボルトで固定する、被災した際に原料の調達が難しくなりそうであれば代替資源を確保するなど、具体的な事前対策を計画・実施していきます。
⑤緊急時の体制の整備
緊急事態が発生した場合の体制や復旧の手順などをまとめていきます。まずは指揮を執る責任者を決めておくことが重要です。万が一、責任者が被災してしまった場合に備えて、代理の責任者も2名ほど決めておくとよいでしょう。
緊急事態発生時の対応は、初動対応と復旧に向けた対応に分けて考えてみてください。たとえば初動対応では安否確認や避難、復旧に向けた対応では取引先との調整や資金の確保などの行動が必要です。
【2】BCMの運用
BCPを策定したら、BCMの運用を行います。BCMを運用していくプロジェクトチームを立ち上げ、実施体制を確立しましょう。BCPは複数の部門に関係が深いため、全社横断的な組織体制が必要です。BCPの訓練や教育、改善などの計画を立て、BCMを運用していきましょう。
ここではBCMの大きなポイントとして、BCPの定着と見直しについて解説していきます。
BCPの定着
緊急事態の際にBCPを機能させるには、従業員に内容をしっかり把握してもらうことが必要です。BCPの内容を社内に掲示するほか、従業員への教育や訓練の実施を行いましょう。
教育に関しては、防災をテーマにグループディスカッションを行ったり、経営者から年に1回BCPの重要性を話してもらう機会を作ったりなどさまざまな方法があります。緊急時に役立つ応急処置の方法を伝える講習など、防災の知識や技能を身につけてもらう教育も必要です。
教育でBCPを浸透させるとともに、訓練を定期的に行うことで、BCPの定着が進みます。BCP訓練については以下の記事を参考にしてください。
記事リンク:BCP訓練とは?目的や進め方、シナリオ例を紹介
https://www.infocom-sb.jp/column/bcp/1401
BCPの見直し
BCPの内容が古くなると、緊急時の実現性が低くなってしまうため、定期的な計画の見直しが欠かせません。
人員の異動があったり、業務体制が変わったり、扱う商品が増えたりした場合は、変更に応じてBCPを改善する必要があります。たとえば安否確認に使う緊急連絡網の更新や、備蓄の入れ替えなどを必要に応じて行うことが重要です。上記とは別に、訓練を経て見つけた課題や問題点も、必ず見直しと改善を行い、BCPの内容を更新してください。
BCMのプロジェクトチームによる更新・改善のほか、経営層による見直しも行いましょう。
BCMSとは

BCMと似た用語に、BCMS(Business Continuity Management System)があります。BCMSは事業継続マネジメントシステムのことで、BCMを継続的に、かつ効果的に運用していくためのシステムを指します。
たとえばBCMがしっかり機能しているかを客観的に判断するために行う、企業の監査人による内部監査や、経営層のマネジメントレビューなどがBCMSの活動に含まれます。
BCPの策定だけでなくBCMの構築が必要
企業における緊急事態への対応力を向上させるには、BCPの策定だけにとどまらず、その有効性をさらに高めるBCMが非常に重要です。BCPを策定する際はBCMの構築もセットで考え、教育や訓練、見直し・改善などの取り組みにも着手しましょう。