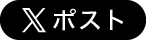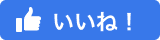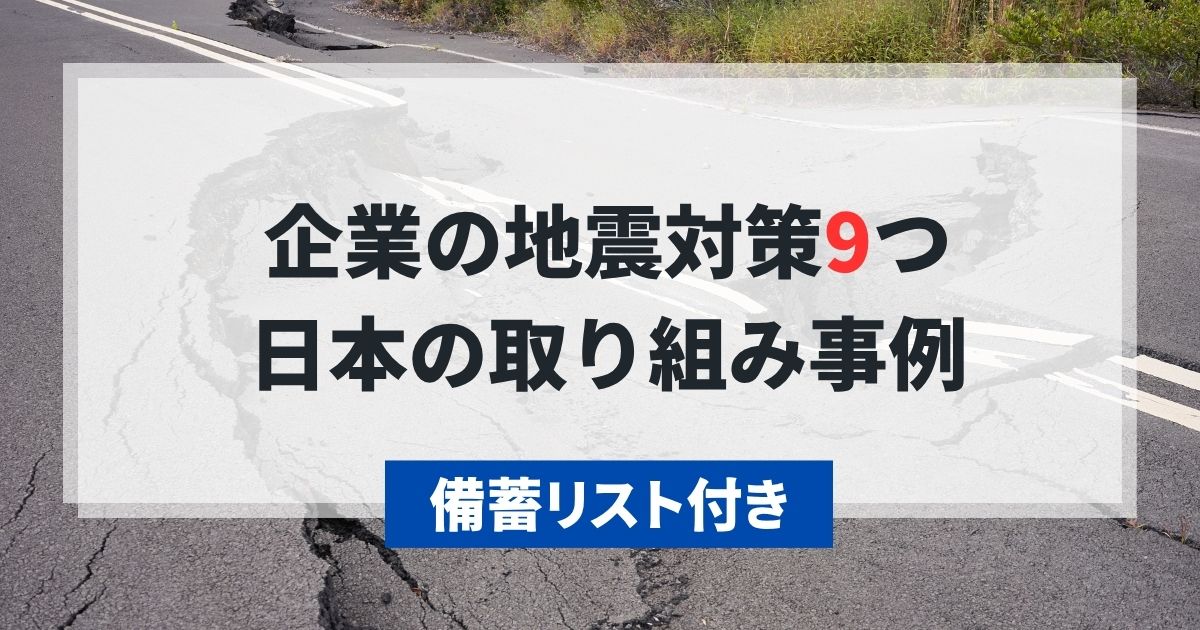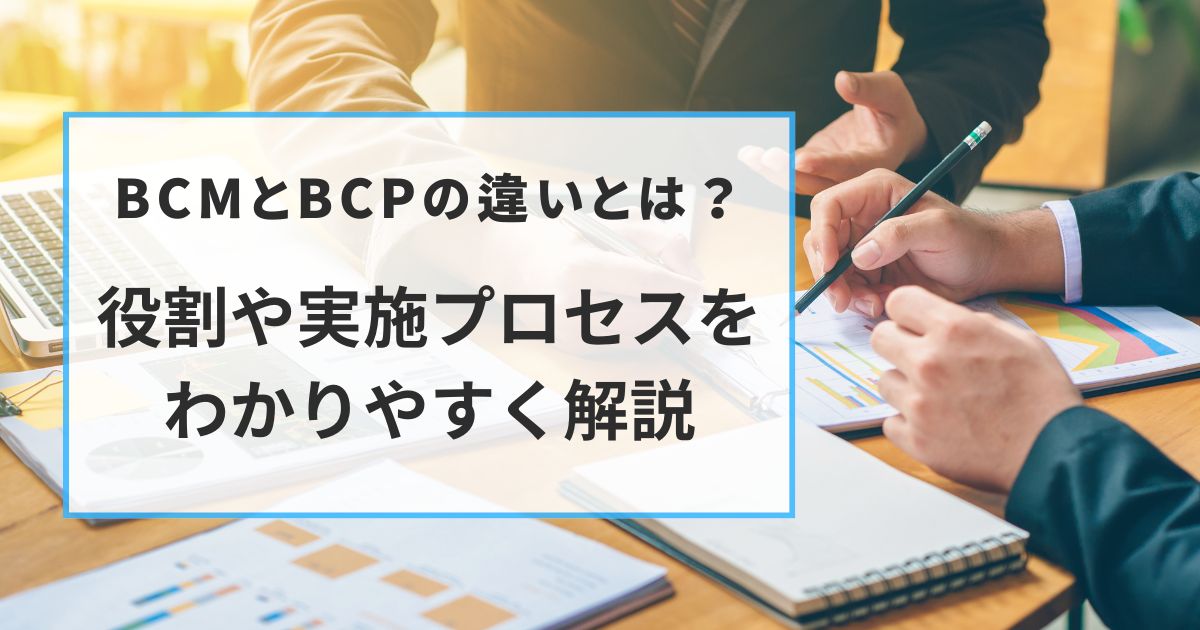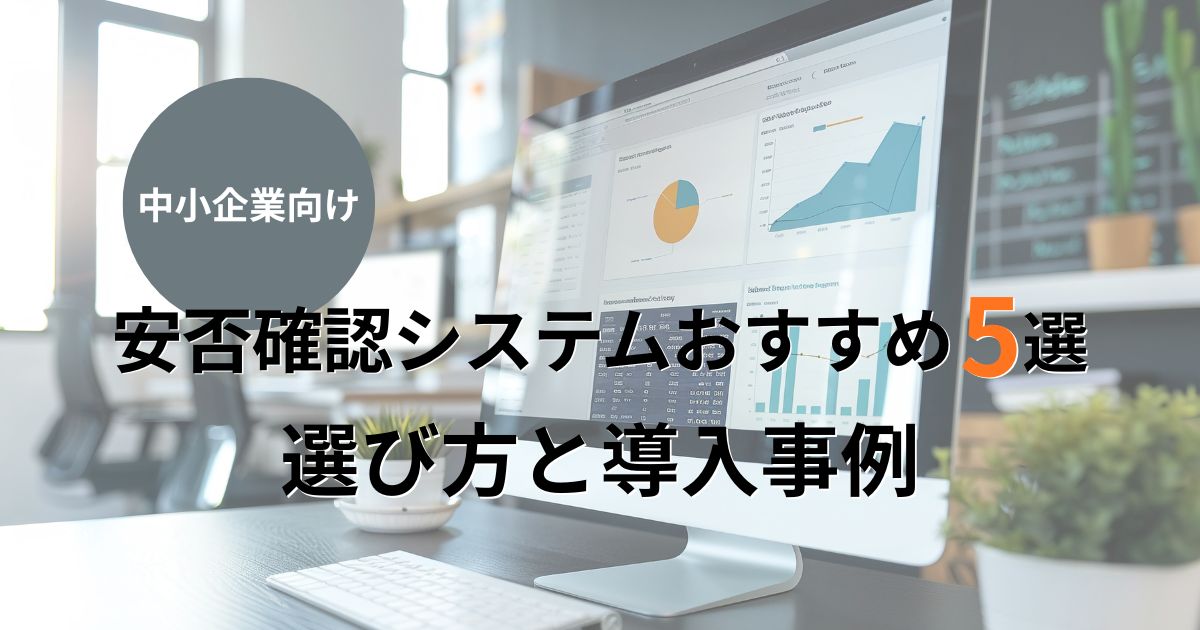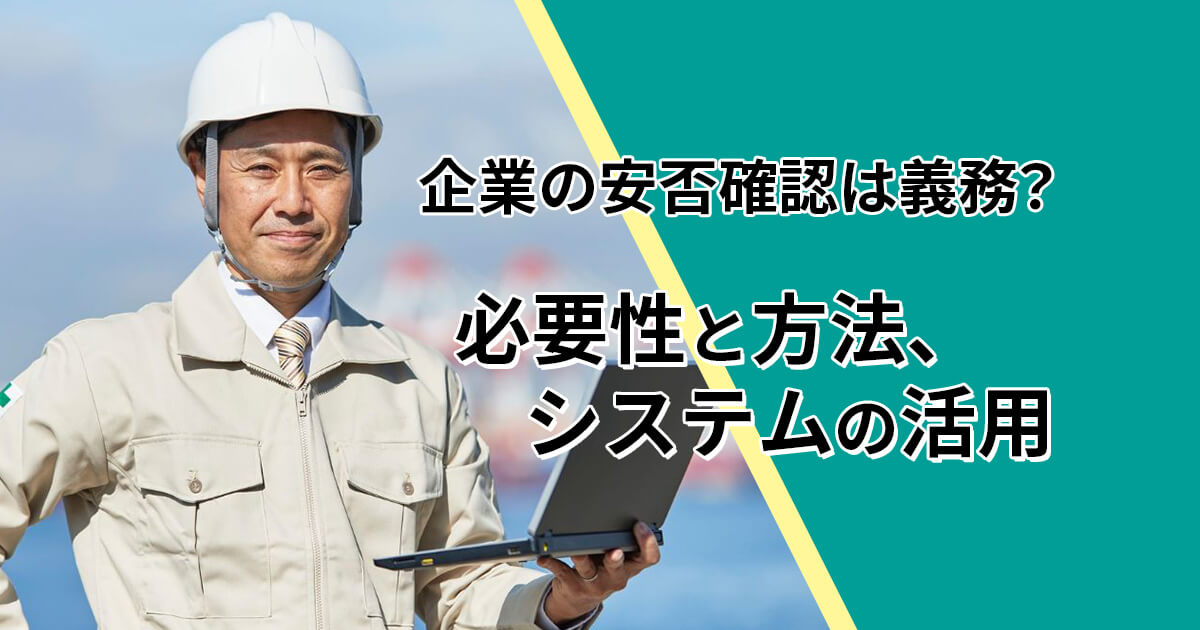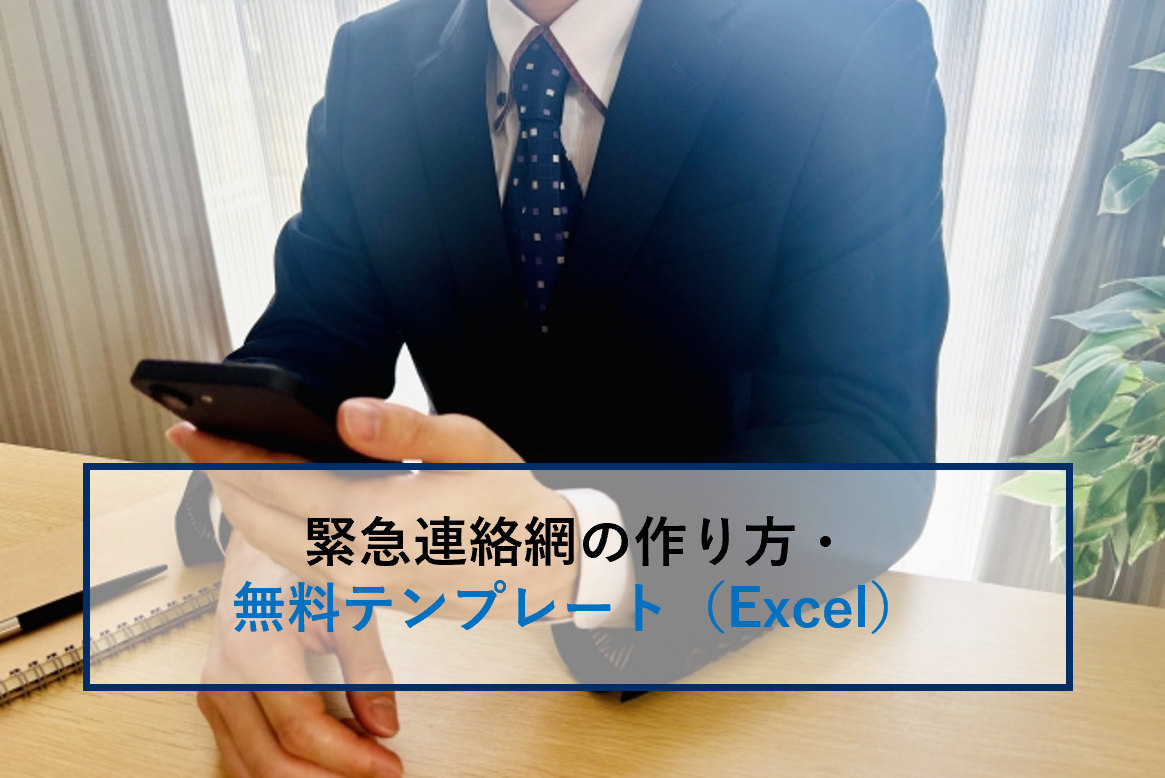目次
地震大国と呼ばれる日本では、いつどこで大規模な地震に見舞われるかわかりません。従業員の命を守るため、かつ事業を継続するために企業はあらかじめ地震対策を講じておく必要があります。
この記事では企業が地震に備えて準備しておくべき9つの項目と、具体的な対策事例を紹介します。地震対策で肝心な備蓄のチェックリストも用意しました。
地震対策の3つのステップ
地震多発国である日本では、大地震の発生が想定されている地域以外にも、いつどこで大きな地震が起こるかわかりません。これまでも大規模な地震により甚大な被害を受けている企業が多いなか、各企業で事前の地震対策が求められています。
地震対策が不十分な企業は、まず以下のステップに従って準備を行っていきましょう。
| ステップ | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 企業防災の目的を明確にする | 「事業の継続または早期復旧」「従業員の安全確保」「二次災害防止」など企業防災で果たしたい目標を定める。 |
| 2 | 地震による被害を把握する | 具体的な対策を考えるため、自社のエリアでどのような地震災害が発生し得るのか、発生した場合に考えられる被害などをあらかじめシミュレーションする。 |
| 3 | 具体的な対策を実施する | 地震による人的被害と物的被害を防止するには、自社にどんな対策が必要か考え、実行する。 |
地震対策の具体的な取り組み9つ

次に具体的な地震対策について、事前に考えておくべき9つの取り組みについて紹介します。
①災害対策組織を構築
地震が発生した際に人的被害と物的被害を抑えるには、全社一丸となって行動する必要があります。そのためには、いざというときに指揮をとる災害対策組織の存在が必要不可欠です。
まずは防災組織や自衛消防組織など今ある組織をベースに、避難誘導係や安否確認係をはじめとした緊急時の担当部門を加えます。緊急時の業務が特定の担当部門に集中していないかなどを確認しながら、人員数と役割分担などを考えましょう。
②安否確認体制の確立
地震発生時の初動対応として、特に重要となるのは従業員の安否確認です。家族の安否が把握できることで復旧活動に集中できるため、従業員の家族の安否確認まで行う企業もあります。
安否確認は安否状況を収集する以外に復旧活動を行える人員を把握する目的もあることから、事業継続においても非常に重要な取り組みといえます。
具体的な対策としては安全確認の手順やルールをまとめた緊急連絡網を作成し、従業員に周知させることが必要です。場合によっては安否確認メールの自動配信や回答の自動集計が行える安否確認システムを導入する方法もあります。
③避難経路の確保
安全な避難ルートおよび避難場所をあらかじめ想定しておきましょう。避難する際の通り道に二次災害を引き起こす可能性の高い危険な建物やブロック塀がないか、ルートが物で塞がれていないかなどを実際に歩きながらチェックします。
また、避難のルールや手順の整備も必要です。地震発生時はすぐに避難を開始するわけではありません。まずは机の下などで自分の身を守り、揺れが収まってから避難行動に移ります。避難する前に、ガスの元栓を締めたり、工場の機械を停止させたりなど二次災害が起きないための対策も重要です。
④オフィスや工場の地震対策を実施
建物や設備の耐震性をチェックし、必要な事前対策を講じましょう。築年数が古い建物や、大きな吹き抜けがある建物などは、耐震性が低いと考えられるため、耐震診断を行い、建物に耐震補強を施すなどの対策が必要です。
手始めに設備や棚などの転倒対策や備品の落下対策などから始めましょう。パソコンが倒れないよう固定したり、保管ラックをボルトで床や壁に留めたりなどの方法があります。
⑤備蓄の用意
地震対策では地震発生から3日分の備蓄を用意することが基本です。以下で備品のチェックリストを用意したので参考にしてください。備品の保管場所は災害時に取り出しやすい場所を選定しましょう。
備蓄リスト
- 飲料水 1人9L(1日3L×3日分)
- 主食(アルファ米やレトルト食品など) 1人9食(1日3食×3日分)
- 毛布 1人1枚
- 簡易トイレ
- ティッシュペーパーやトイレットペーパー、ウェットティッシュなど
- 携帯電話
- 懐中電灯
- ランタン
- 乾電池
- ビニール袋
- ロープ
- ガムテープ
- ブルーシート
- 給水用ポリタンク
- カセットコンロ
- 救急箱
- ヘルメットなどの防災用品
⑥情報資産を守る対策を実施
顧客情報や財務情報、製品の技術情報などの情報資産は、企業活動をするうえで非常に重要なものです。災害時にデータの消失やシステムの破損などが起きないよう、事前対策の実施が必要になります。
たとえば事前にデータのバックアップをとるなどの対策を講じておきましょう。その際にバックアップデータのひとつを、事業所とは離れた遠隔地で保管することがポイントです。東日本大震災の津波でバックアップデータ自体が消失してしまったケースもあるため、あらゆる事態を想定した対策が欠かせません。
⑦地震対策のマニュアルを作成
地震発生時の被害を抑えるために、災害時の行動指針をまとめたマニュアルの作成を行いましょう。マニュアルでは上記で解説した安否確認方法や避難場所のほか、災害対策組織の各部門の業務など、必要な情報を網羅することが必要です。かつ誰もがわかりやすく、理解しやすいよう簡潔に内容をまとめることが求められます。
マニュアルは作成して終了ではなく、定期的な見直しも重要です。事業内容や人員の変化などに伴い、適宜見直しと修正を行いましょう。
⑧防災訓練と教育
災害対応力を高めるには、従業員に対して事前の防災教育や防災訓練などを行い、意識づけることが必要です。
防災教育は作成したマニュアルを浸透させるための研修などを指します。防災に対してより理解を深められるよう、地震発生のメカニズムや地震の被害事例、自社の地震リスクなども盛り込むとよいでしょう。
防災教育を実施したら、理解度を確かめるための防災訓練が重要です。地震を想定して、避難訓練や安否確認訓練などを実施しましょう。防災訓練は一度実施したら終わりではなく、繰り返し行うことがポイントです。
⑨保険への加入または補償内容の見直し
地震の備えとして、企業向けの地震保険へ加入しましょう。保険料をはじめ、地震による被害をどこまでカバーしてもらえるのかなどを確認し、自社にあった保険を選ぶことが大事です。
すでに地震保険に加入している場合は、補償内容などに過不足がないか一度確認することをおすすめします。
日本における取り組み事例

インフォコムでは、弊社サービスを導入している企業が情報交換できる座談会などを定期的に開催しています。能登半島地震からの学びと危機管理の改善点について意見を交換した座談会から、地震対策の取り組み事例をご紹介します。
地震における情報共有
メーカー企業Aでは災害対策本部の設置基準を「震度6以上」と定めて準備していました。しかし能登半島地震では建物を襲った地震が震度5強だったことなどから災害対策本部を設置しませんでした。その代わり、現地の総務と東京本社で対応を行ったところ改善すべき点がいくつか見えてきたといいます。たとえば現地と本社の連絡がスムーズにできなかったり、被災状況が把握しづらかったりなどの問題点が生じました。現在、それらの問題点を解決するため、緊急時の情報収集・共有やコミュニケーションが可能なシステム「BCPortal」の運用を考え、準備しています。
安否確認体制
メーカー企業Bでは安否確認システムの「エマージェンシーコール」を導入し、自動送信機能を設定して地震に備えていました。さらに余震に対して何度も安否確認の連絡が回答者へ送られないよう、再通知抑制機能も利用。地震発生から24時間以内の余震に対しては、安否確認を送らない設定にしていました。しかし能登半島地震では最初の地震から24時間を過ぎてからまた大きな地震が発生したために、1回目の安否確認のフォローが不十分なまま2回目の安否確認連絡が発生してしまいました。こちらの企業では再通知抑制機能の設定を見直し、安否確認体制の改善を目指しています。
上記のように地震対策は一度計画・実行して終わりではなく、見直しを行いながら改善していくことが非常に重要です。
地震対策だけでなくBCPの策定を
日本には大規模地震に見舞われ、企業活動を停止する事態に陥った事例が大変多くあります。人的被害や物的被害を抑える地震対策だけでなく、緊急時に事業を継続させるための対策としてBCPの策定についても検討してみてください。
BCPは重要業務の継続を目的とした計画のことです。自然災害に限らずあらゆるインシデントを想定した計画のため、パンデミックやシステム障害などさまざまなリスクへの対策を考える企業はぜひBCPの策定を視野に入れましょう。
人命・企業を守るための地震対策が必要
地震大国の日本ではどの地域においても大規模な地震に見舞われる可能性があります。そのためすべての企業が人命と自社を守るために地震対策を行う必要があるといえます。
今回、記事で紹介した対策を参考に、まずはできることから始めてみましょう。その後は従業員への教育と訓練などを通して、計画を見直し・改善していくことで、さらに災害への対応力を高めることができます。